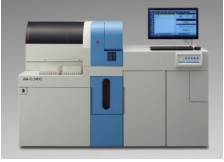東ソーはこのほど、「プラチナくるみん認定」を取得した。「くるみん認定」は、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境整備に向けた行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成して一定の基準を満たした企業を、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣が認定するもの。

くるみん認定企業のうち、両立支援の制度の導入や利用が進み、より高い水準の取り組みを行った企業は、優良な「子育てサポート企業」として「プラチナくるみん認定」を受けることができる。
同社では、「ワークライフバランス推進」「女性従業員の更なる活躍推進」「男性従業員の育児参加促進」「健康経営の取組推進」を行動計画に掲げており、所定外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、男性の出産育児休暇及び育児休業の取得促進、育児休業(一部)・看護休暇の有給化、健康経営優良法人の認定取得など、様々な取り組みを実施してきた。
同社は、「働きやすい職場づくり」「ダイバーシティ」をCSR重要課題として位置づけており、今後も多様な人材がやりがいをもって働き続けられるよう職場環境を整備し、ワークライフバランスの実現を積極的に推進していく。