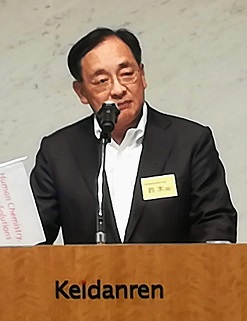コベストロの2019年12月期第2四半期決算は、 グループの総売上高が前年同期比17%減の約32億ユーロ、EBITDAは同53%減の4億5900万ユーロ、純利益は同69%減の1億8900万ユーロとなった。
主要製品の販売量は同1%増加したが、販売価格の下落により減収。EBITDAは第1四半期の水準を維持したものの、非常に好調だった前年同期を大きく下回る結果となった。利益の減少は、主にポリウレタン事業とポリカーボネート事業での利益率の低下によるもの。ただ、同社では利益の減少は予想通りとしている。
セグメント別では、ポリウレタン事業の主要製品の販売量は同1%増。売上高は競争激化による販売価格の下落の影響を受け、同24%減の14億8900万ユーロ。販売価格の下落による影響はEBITDAにも顕著に見られ、同71%減の1億7200万ユーロとなった。
ポリカーボネート事業の主要製品の販売量は同4%増。電気・電子産業や建築産業が貢献した一方で、自動車産業の販売量は減少した。売上高は同15%減の8億9800万ユーロ。EBITDAは同46%減の1億5400万ユーロ。これは主に販売価格の下落によるもの。
塗料・接着剤・スペシャリティーズ事業の主要製品の販売量は同5%減。売上高は同1%減の6億2100万ユーロ。EBITDAは同8%増の1億5千万ユーロ。為替レートの変動と、日本を拠点とするディーアイシー・コベストロ・ポリマー(DCP)の株式の段階的取得がプラス効果をもたらした。DCPの持株増加は、EBITDAにも臨時のプラス効果をもたらしている。
通期の業績見通しについては変更せず、主要製品の販売量を一桁台前半から半ばの増加率、EBIDAは15億ユーロから20億ユーロの間と予測している。