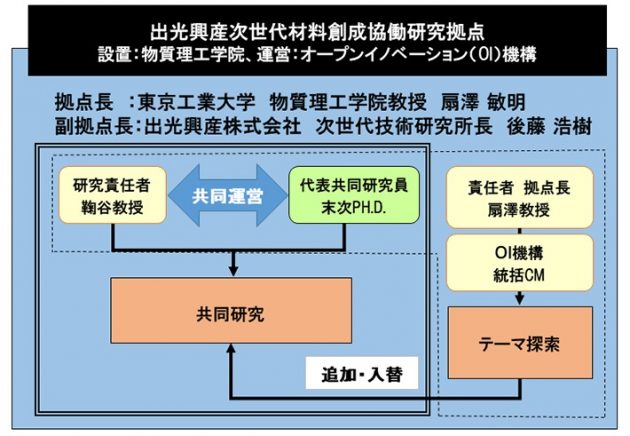東レグループは、1926年の創業以来、「社会への奉仕」を存立の基礎とし、素材には社会を変える力があると標榜している。2018年に「東レグループ サステナビリティ・ビジョン」を公表し、2050年に向けた、東レグループの事業推進による社会への貢献と、それに伴う環境負荷の低減の両面について、当社の考え方と中長期の取り組みを示した。
東レグループが応えるべき課題を推進するために、次期長期経営ビジョンと次期中期経営課題では、引き続き、「グリーンイノベーション事業拡大プロジェクト」と「ライフイノベーション事業拡大プロジェクト」の2つのプロジェクトを通じて積極的な事業拡大を推進していく。
長期戦略では「事業を通じた社会貢献」という創業以来引き継がれてきた考え方に基づいた「東レ流の経営」を実践することで、単に事業規模を拡大するのではなく、社会から尊敬される企業体として存在することを目指している。
2020年度は、次期長期経営ビジョン、次期中期経営課題のスタートの年だ。全社員が一丸となり、これを実現するための課題に取り組み、目標を達成することが重要である。皆さんもこれから始まる東レでの仕事に積極的にやりがいを持って取り組んでほしい。
また、当社はグローバルに事業展開する企業グループであり、長期的視点に立ちその国の社会発展・産業振興・輸出拡大・技術水準向上への寄与を海外展開の基本方針としている。誠実な企業市民として高い倫理観を持ち、社会貢献を果たす企業である。これらの特徴は、社員が長い歴史の中で誇りを持って築き上げてきたことだ。今日から東レ社員となる皆さんにも是非、この文化・伝統をしっかりと身につけてもらいたい。
最後に、入社に際し皆さんに四つのことを期待する。「『高い志』と『大きな気概』を持って仕事に取り組むこと」「現場に立脚した『第一人者』、世界トップレベルの『専門家』になること」「グローバルに通用するしっかりとした考え方・価値観・判断基準を持つこと」、そして「『社会的責任』を常に意識し、高い倫理観と強い責任感を持って行動すること」だ。
これら4つのポイントをしっかりと胸に刻み、健康で明るく前向きに頑張って、有意義な会社生活を切り開いていただきたい。