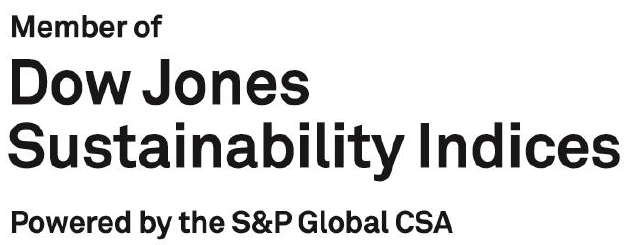旭化成は8日、製造統括本部 水島製造所(岡山県倉敷市)が、経済産業省の制定する「高圧ガス保安法における新認定事業者制度」において特定認定事業者(通称:スーパー認定事業者)に11月25日付で認定されたと発表した。
 大氣隆環境安全部長、井谷圭仁水島製造所長(右)
大氣隆環境安全部長、井谷圭仁水島製造所長(右)
同制度ではプラントの高経年化、熟練従業員の退職などに対応するため、高度なリスクアセスメント/教育訓練の実施、IoT・ビッグデータの活用、第三者機関による保安力評価の活用など、より高度な保安への取り組みを行っている認定事業者を「スーパー認定事業者」として認定するもの。
認定を受けた事業者は、設備の検査方法・点検周期、連続運転期間などの自由度が高まるといった自主保安の規制合理化が適用され、より柔軟かつ効率的な事業運営が可能となり、競争力強化にもつながる。水島製造所は同社グループとして初めてスーパー認定事業者となった。
 スーパー認定事業者に認定された水島製造所
スーパー認定事業者に認定された水島製造所
同製造所は、「安全の確保は経営の最優先課題」であり、企業活動を通じた社会貢献を果たしていく上では「安全安定操業こそが使命」との考えから、「社会から信頼される製造所」を目指してきた。そのために思考力・実行力を備えた人財の育成、網羅的で信頼性のあるリスクアセスメントの実施およびその評価に基づくリスクの継続的低減と適切な運転・設備管理、設備異常を早期検知するためのIoTやAI、ビッグデータを活用した先進技術の導入を強力に進めてきた。
今後は、スーパー認定事業者として従来の取り組みを継続的に高度化し、ステークホルダーから信頼されるよう努力するとともに、社会の持続的発展に貢献していく。