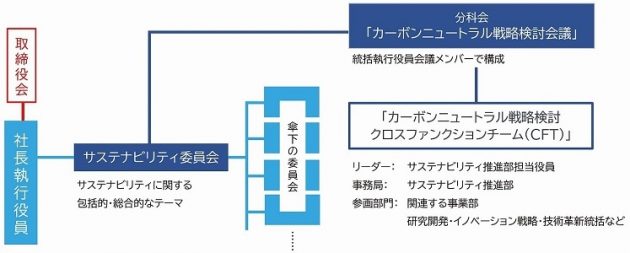[出光興産・人事②](4月1日)▽人事部労務・厚生担当部長兼人事サポート課長兼健康保険組合理事長兼企業年金基金理事長青木信浩▽人事部採用教育課長兼石岡研修センター長兼ジクシス久原淳平▽デジタル変革室次長兼事業変革課長大澤一成▽同室次長兼テクノロジー課長佐藤勉▽調達部次長兼全社調達課長兼DTKプロジェクト畑間源一▽同部調達戦略課長御厨千恵▽情報システム部次長兼共通IT推進課長澤井隆慶▽同部システム統合担当部長松木敬吾▽経営企画部投資・M&A担当部長兼企画二課長菊池一美▽モビリティ戦略室次長兼企画課長福地竹虎▽資源部次長兼石油開発欧州統括課長兼DTKプロジェクト綿引勇治▽同部アジア事業担当部長松田学▽同部主幹部員兼出光大分地熱社長兼滝上事業所長八田幹人▽同部地熱事業室事業推進課長阪本克彦▽同部同室企画開発課長塩原正彦▽石炭・環境事業部販売一課長齋藤仁史▽販売部ビジネスデザインセンター副センター長吉野聡▽リテールマーケティング部リテール政策課長渡部務▽同部販売情報システム課長仲谷友良▽流通業務部受注配送管理センター所長兼統括課長兼ジェイ・エル・エス萩原一美▽同部新潟石油製品輸入基地所長兼ジャパンオイルネットワーク(新潟)加藤武志▽同部海運課長小松規流▽同部安全品質管理課長石原慎一▽産業エネルギー部営業一課長福井義則▽製造技術部工務総括課長岡山昌雄▽生産技術センター管理課長内田陽介▽同センターエンジニアリング室プロセス設計グループリーダー兼出光エンジニアリングエンジニアリング本部エンジニアリング部浴森昇平▽同センター同室機械設計グループリーダー兼同社同本部同部土谷武輝▽次世代技術研究所安全環境・設備課長栄田暢次▽同研究所研究企画課長杉山丈志▽電子材料部次長兼事業統括グループリーダー兼DTKプロジェクト中島光茂▽同部事業企画担当部長金重雅之▽同部安全・品質保証グループリーダー伊藤和彦▽同部電子材料開発センター副所長竹内邦夫▽同部無機材料開発グループリーダー刈間雄祐▽同部電子材料開発センター知財戦略グループリーダー前田元輝▽アグリバイオ事業部アグリ事業一課長辻幸二▽同事業部アグリバイオ技術課長稲井康二▽リチウム電池材料部マーケティング担当部長柴田康雅▽同部管理グループリーダー重藤匡▽同部材料開発センター所長遠藤英司▽同部同センター知財戦略グループリーダー土屋亮▽同部同センター先進材料研究グループリーダー三輪徳昭▽電力・再エネ電源事業部海外再エネ課長和田敬良▽同事業部バイオマス発電課京浜バイオマスパワー発電所長兼製造技術部川崎事業所長佐々木雄一▽基礎化学品部生産管理・技術戦略担当部長具嶋文彦▽同部国内外事業・戦略企画担当部長宮岸信宏▽同部総括課長市成誠史▽同部戦略企画課長香川雄作▽同部オレフィン課長荒尾友紀▽同部アロマ課長蜂須賀祐▽同部生産管理課長兼千葉ケミカル製造有限責任事業組合坂元洋明。
出光興産 人事②(4月1日)
2021年3月17日