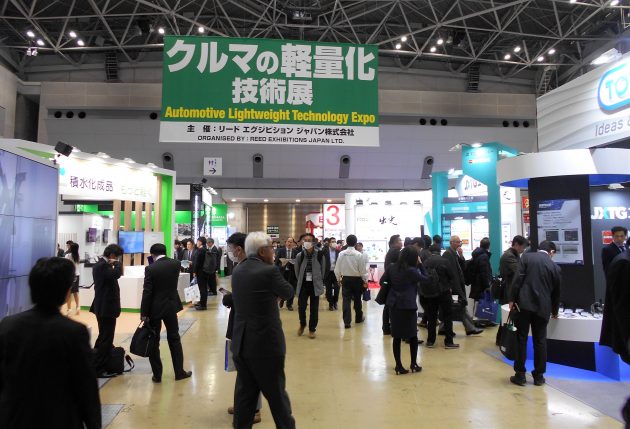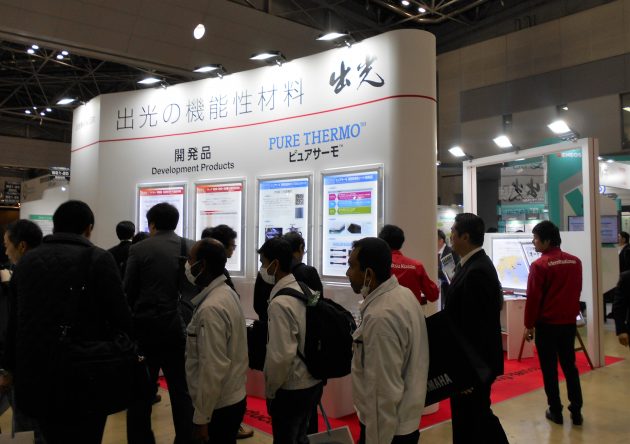出光興産は日本政策投資銀行(DBJ)の「BCM格付融資」制度で、最高ランクの「ランクA」を石油元売り企業として初めて取得し、17日に格付認定証を受領した。BCM格付融資とは、DBJが開発した独自の評価システムにより、防災と事業継続対策に優れた取り組みを行っている企業を評価・選定し、その評価に応じて融資条件を設定するもの。
「BCM格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資メニューで、格付はランクAからランクCまでの3区分で認定される。同社は「防災力」と「事業継続力」について、第3者からの客観的な評価を受けることによる、企業としてのレジリエンス(強靭性)の確認と向上に加え、昭和シェル石油との経営統合による事業基盤拡大に対応した、資金調達と調達条件の多様化を目的に、BCM格付を取得した。
ランクAに認定されたのは、トップコミットメントの下、地政学やサイバーリスクなども踏まえたオールハザードに対応したリスクマネジメント体制を構築し、事前投資によるリスクコントロールやリスク顕在化時の財務影響度分析を踏まえ、多様なリスクファイナンスを準備するなど、経営と一体となったレジリエンス強化に努めているため。
また、石油供給の継続は人命に関わるとの社会的使命感の下、海外のリスクエンジニアサーベイを導入し、国際水準での安全・防災点検と対策など、業界に先行した設備耐震化対策の徹底に加え、業界共助である「災害時石油供給連携計画」に基づき、日本全国の石油供給の継続に取り組む体制を構築していることもある。
さらに、自衛隊をはじめ、外部ステークホルダーも巻き込んだ多様な訓練の実施などを通じ、事業継続計画の不断の改善に取り組むとともに、高度なリスクマネジメントを支える人材育成の体制を整備するなど、有事対応の実効性向上に努めている点も評価された。
同社は2003年から首都直下地震、南海トラフ巨大地震、新型インフルエンザBCPを策定し、毎年の訓練結果と外部からの意見をもとに、計画の見直しを続けている。今後も災害に対する強靭性と実践的対応力の強化に努め、エネルギーの安定供給を通して社会に貢献していく方針だ。