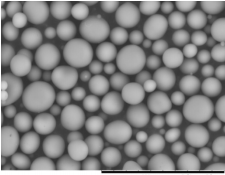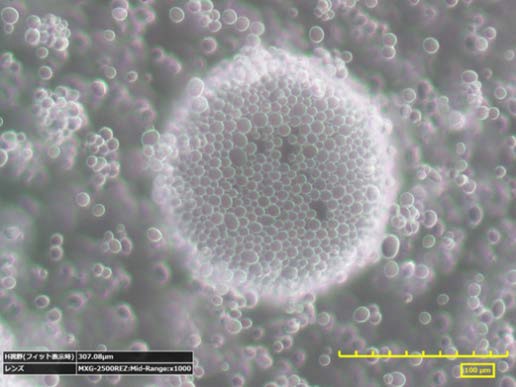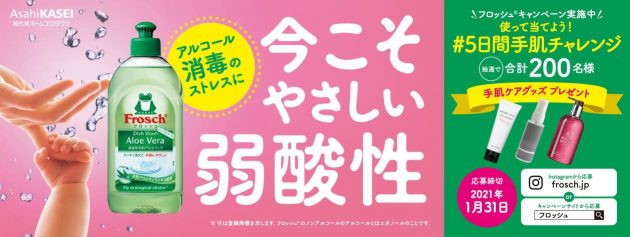三菱ケミカルが出資しリサイクル事業を手掛けるリファインバースは26日、リサイクルナイロン樹脂「リアミド」事業のさらなる拡大のため、新たに船舶係留用ロープのマテリアルリサイクル(MR)を開始すると発表した。
昨年の販売開始以降、リサイクルナイロン樹脂「リアミド」には、海洋プラスチック問題やサーキュラーエコノミーへの社会的関心の高まりを背景に、数多くの引き合いがあり、原料ソースの拡大が必要となっている。
同社はこれまで、廃棄漁網とエアバッグ工程端材を主要な原料として「リアミド」を製造販売してきたが、今回、ナイロン製船舶係留用ロープについても同社が開発したプロセスによりリサイクル可能であることを確認した。今後、ナイロン製船舶係留用ロープを新たな原料として「リアミド」事業をさらに拡大していく。
同社は、リサイクルナイロン樹脂「リアミド」の原料ソース拡大、および材料開発・用途開発による再生素材の付加価値向上を進め、サステナブルな社会の構築に具体的に貢献しながら、事業拡大を推進していく考えだ。