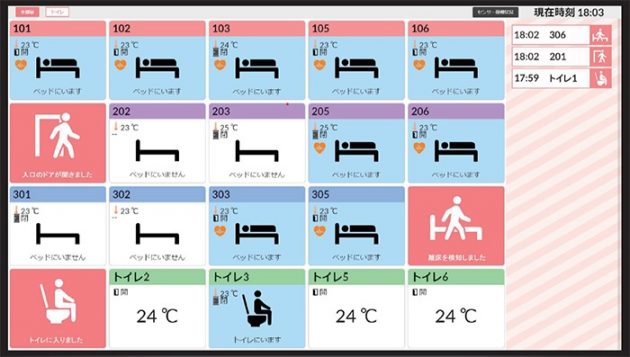住友理工と産業技術総合研究所(産総研)はこのほど、産総研のつくばセンター内に「住友理工-産総研先進高分子デバイス連携研究室」を設立したと発表した。自動車業界は「CASE」(コネクト、自動運転、シェア、電動化)など新規の機能・役割で、100年に1度の大変革期を迎えている。
 ステアリングタッチセンサー
ステアリングタッチセンサー
住友理工は新たなニーズを取り込むため、防振ゴムやホースの研究開発で培った「高分子材料技術」「総合評価技術」によりハンドルやシートへの圧力や接触を検知・可視化するセンシングデバイス「スマートラバー(SR)センサ」技術を開発し、この変革に応えた技術・製品を生み出してきた。
今回提携する産総研の「情報・人間工学領域ヒューマンモビリティ研究センター」は、人を計測し理解する基盤研究の下、運転支援や自動運転技術をはじめ、歩行から公共交通機関まで様々な移動手段の支援技術と移動価値向上技術の研究開発を行い、人間を中心にモビリティ全体を最適化し、ライフスペースの拡大を図っている。
連携研究室は住友理工の先進技術と産総研の研究開発の成果を融合し、生活全般での人々の安全・安心・快適への寄与を目的に設立した。具体的には、センシングデバイス実装車両による実際の再現走行実験で、生体情報・状態の推定可能限界を明らかにする。
例えば、「SRセンサ」をシートに内蔵またはクッション形状に加工して座面に置き、座面の圧力変化からドライバーの心拍・呼吸・体の動きなどを検知し、疲労や居眠り、急病予兆などドライバーの状態を推定することで、警告や運転支援システムの作動、外部への通報などにつなげるドライバーモニタリングシステムを開発する。
 ハプティクスインターフェース
ハプティクスインターフェース
また、ステアリングタッチセンサや「SRセンサ」の柔軟・通電性を利用したハプティクスインターフェース(信号入力で振動)などで自動運転の安全性を確保していく。 その中で官能定量化の先端的技術やデータ解析技術の深化、既存技術とデジタルの融合による技術革新など総合評価技術を高度化し、各種開発途上技術を確立し、高付加価値の製品群とソリューションを創出することにより、グローバル・システムサプライヤーとしてモビリティ社会のさらなる発展に貢献することを目指す考えだ。