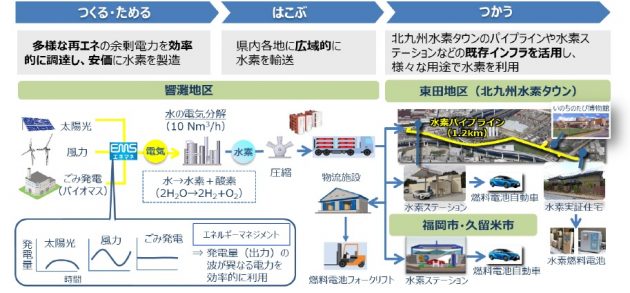三菱ケミカルはこのほど、グループ会社である三菱ケミカルアクア・ソリューションズ(MCAS)が、環境省から「令和2年度気候変動アクション環境大臣表彰」を受賞したと発表した。
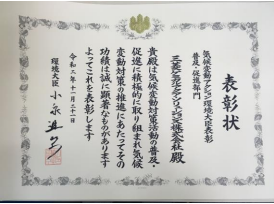
環境省では今年度より、気候変動の緩和と気候変動への適応に顕著な功績のあった個人または団体に対し、その功績をたたえる「気候変動アクション環境大臣表彰」を実施。今回、MCASがケニアやミャンマーで行ってきた塩水化・高濁表流水の浄化事業の活動が評価され、同表彰の普及・促進部門(適応分野)で受賞者の1つに選定された。

MCASが事業を展開するケニアやミャンマーでは、気候変動の影響を受け、乾季の河川水位低下に伴う海水遡上(表流水の塩水化)や、雨季の長期化による表流水の高濁度化が深刻化。MCASでは、このような水質が不安定な水源に対し、これまで培ってきた水処理技術を活用して、飲用に適した安全な水を提供するための事業を行っている。また、膜ろ過プラントの運転・維持管理については、現地の水道公社職員に技術移管するだけでなく、遠隔監視システムにより、日本からもモニタリングや技術サポートを行える体制を構築している。
MCASでは今後も、安全・安心な水の供給を通じて、三菱ケミカルホールディングスグループの目指す「KAITEKI」の実現に貢献していく。