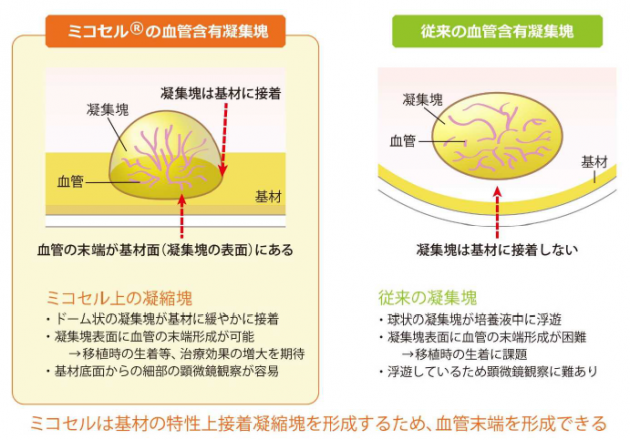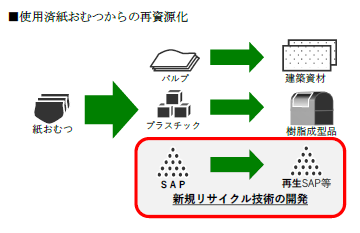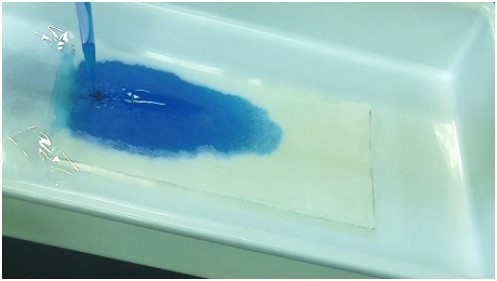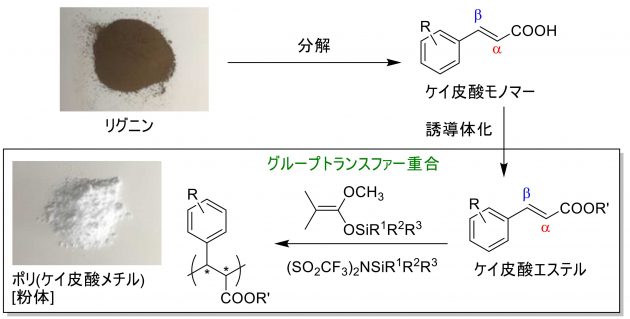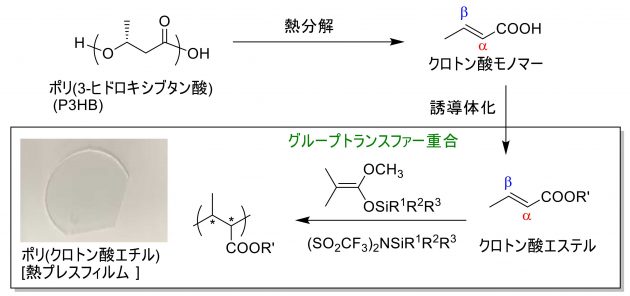日本触媒は11日、紙より薄いフィルム光源(「iOLED」フィルム光源)について、パイロットラインでの製造を開始すると発表した。顧客の様々なニーズに対応するために一定量のサンプルを供給することで早期の製品化を目指す。

「iOLED」フィルム光源は、有機ELの長年の課題であった大気中の酸素や水分による素子の劣化を、日本触媒とNHKとの共同開発による材料や素子技術(iOLED技術)により克服していることに加え、厚さ0.1mm以下と紙より薄く、高い柔軟性も実現している。同社には、自動車業界、服飾業界、包装業界、美容・医療業界など多岐にわたる業界から問い合わせがあり、これまで少量のサンプル提供を行ってきた。
今回パイロットラインを立ち上げたことで、より大規模で本格的なサンプル試験が可能になる。製造する基板の最大サイズは200mm×200mmだが、さらに一部製造ラインを自動化することで、生産能力を10倍以上に増強した。このパイロットラインを活用して、様々な開発ステージの顧客に対して希望の使用形態に合った色、形、特性を持ったサンプルを提供していく。
同社は、この「iOLED」フィルム光源の新しい光をもって、明るい未来を創造していくと共に、今後も独創的で優れた技術を開発・企業化し、企業理念「TechnoAmenity~私たちはテクノロジーをもって人と社会に豊かさと快適さを提供します」の実現にまい進していく考えだ。
なお、12月にオンラインで開催される新機能性材料展において「iOLED」フィルム光源を紹介。同社のブースでは、薄さを体感する動画などが視聴できる。