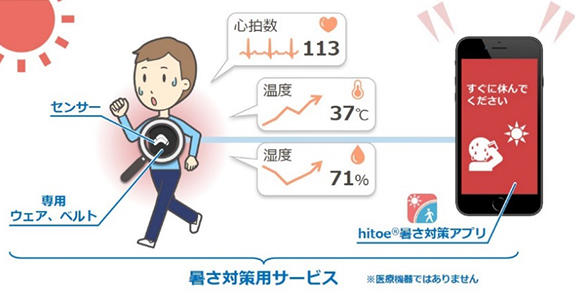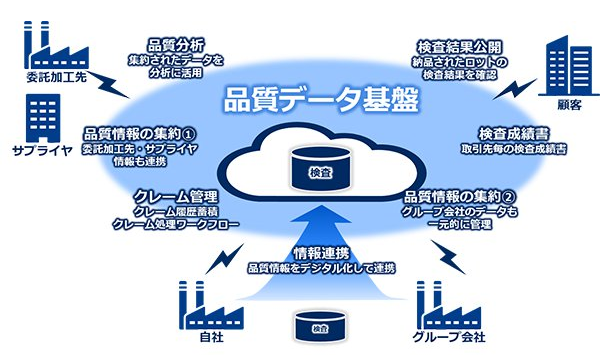東レはこのほど、液晶ディスプレイ用部材「SCOシート」がSID(国際情報ディスプレイ学会)の〝Display Industry Award:Display Component of the Year〟を受賞した。今回の受賞は、世界で初めて有機発光材料を活用し液晶ディスプレイの高色域化に貢献できる、毒性元素を含まない環境調和した技術を創出したことが評価された。
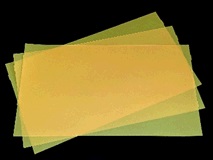
従来の液晶ディスプレイは、赤や緑の発光に無機蛍光体が使用されている。無機蛍光体は、耐久性は高いものの、発光スペクトル幅が広いため色純度が低下する課題があり、ディスプレイとして表現できる色域には限界があった。
これに対し同社は、これまで有機EL用発光材料開発で培った分子設計、合成、精製技術を活用し、従来の無機蛍光体に対し、シャープな発光スペクトルを示す高色純度の赤色および緑色の有機発光材料を開発。有機発光材料は耐久性の向上が課題だったが、独自の発光材料分子設計により、実用化に耐えうる耐久性の確保に成功した。

これらの有機発光材料を用いて開発した液晶ディスプレイの高色域化に貢献できる「SCOシート」は、DCI規格と呼ばれる色域規格、Adobe規格と呼ばれる色域規格のカバー率について、どちらも99%以上の両立が可能。その結果、従来ディスプレイに比べて、より色鮮やかな表示ができる。また、有機材料で構成されているため、重金属のような毒性元素も含まれておらず、環境にやさしいディスプレイ部材だ。
ディスプレイ技術は年々進化を遂げており、4K、8Kといった画面解像度の高解像度に加えて高色域化も要望されており、ハイエンドディスプレイの市場もますます拡大していくと予測されている。
東レはこの業績で培った有機光機能材料分子設計技術をさらに深化させ、有機材料の新たな可能性を切り拓き、企業理念である「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」の具現化に取り組んでいく考えだ。