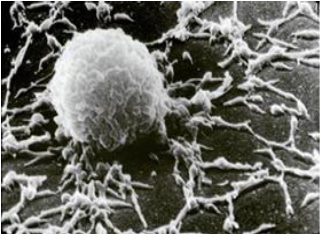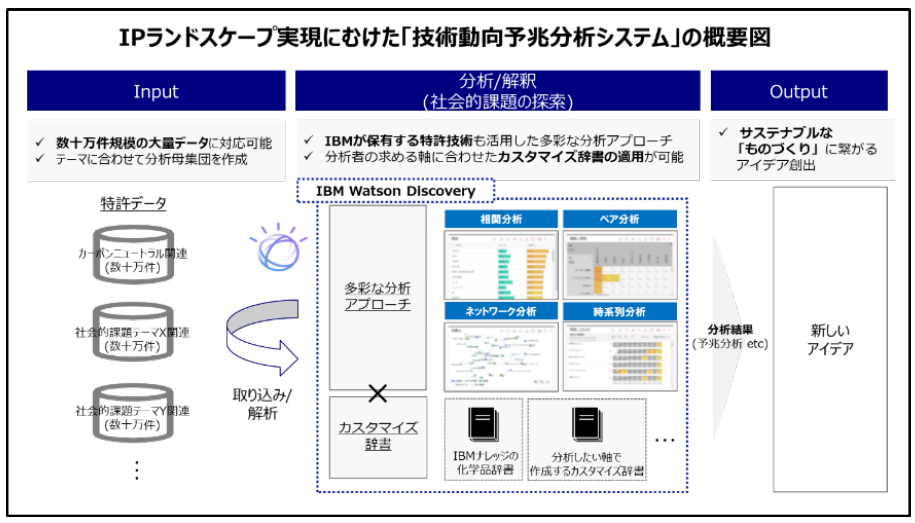帝人はこのほど、炭素繊維の製造に際してのCO2排出量の算出方法を確立し、同社が展開する炭素繊維についてライフサイクルアセスメント(LCA)の対応が可能になったと発表した。炭素繊維のLCA対応を可能にするのは業界初となる。
同社は、炭素繊維製造に際してのCO2排出量の定量化を可能とする独自の換算システム構築のため、スポーツ・レクリエーション用途や産業用途で使用される炭素繊維フィラメントの製造工程におけるCO2排出の評価から着手。今回、航空機用途向けの炭素繊維フィラメントの評価を完了したことで、あらゆる用途でCO2排出量の算出が可能となった。
この算出手法は、国際的に認められた外部機関よりISO14040とISO14044の認証を受けており、同社の製造工程のみならず、顧客の製造工程における評価にも適応できる。そして、LCAの実施により製造プロセスの改善ポイントを明確化できるため、CO2排出量の低減に向けたより良い方策の検討が可能となる。
帝人では、すでに炭素繊維フィラメントの製造工程から評価を開始、今後は短繊維やプリプレグなどの中間材料へと対象範囲を順次拡大していく。また、最終製品メーカーなど、サプライチェーンを成すパートナー企業との連携により、同社の炭素繊維製品のライフサイクル全体についても評価を実施していく。