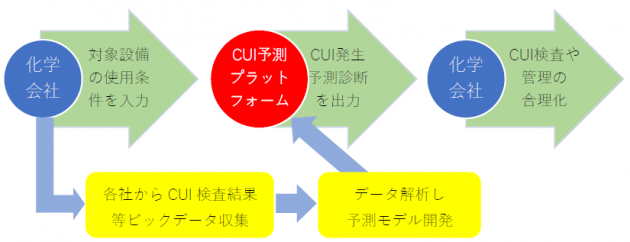昭和電工は8日、産業向け自動化ソリューション事業を手掛けるメキシコのAMI Automationの株式50%を取得したと発表した。なお、今後5年以内に残りの株式を取得するオプションを保有している。
AMIは、電炉向けの運転最適化ソフトウェアや電極制御システムを取り扱うMeltshop Solutions事業、各種産業向けの自動化・制御ソリューションを手掛けるIndustrial Systems事業をグローバルに展開。中でもAMIの電極制御システムは、生産量ベースで北米の約90%の電炉鋼生産に活用されている。
昭和電工は従来から、電炉特性に合わせてカスタマイズした高品質な黒鉛電極を提供し、顧客が高品質な電炉鋼を高効率に生産することに貢献してきた。AMIのMeltshop Solutions事業の手掛ける電炉の運転最適化サービスと連携することで、電極のパフォーマンス向上と電炉運転の一層の生産効率化や省エネルギー化、温暖化ガス排出量の削減に貢献するソリューションサービスを提供することが可能となる。
また、Industrial Systems事業の知見を昭和電工の製造工程に展開することで、黒鉛電極の更なる効率的な生産を実現し、顧客のビジネスにサステナブルな価値を提供するとともに、黒鉛電極市場における昭和電工グループのグローバルリーダーとしてのポジションをさらに強化することを目指していく。
AMIは自動化・制御ソリューション事業のプレミアインターナショナルカンパニーとして、産業プロセス自動化のための革新的製品・ソリューションを提供。Meltshop Solutions事業は、30年以上にわたり、最新の自動化・制御技術の活用により電炉の効率的な運転に貢献し、電炉最適化における世界的なイノベーター・リーダーとして認識されている。
昭和電工は、黒鉛電極事業を含む様々な事業・生産プロセスへAMIの持つ自動化・制御技術を活用することにより、両社の更なる事業拡大を目指していく。