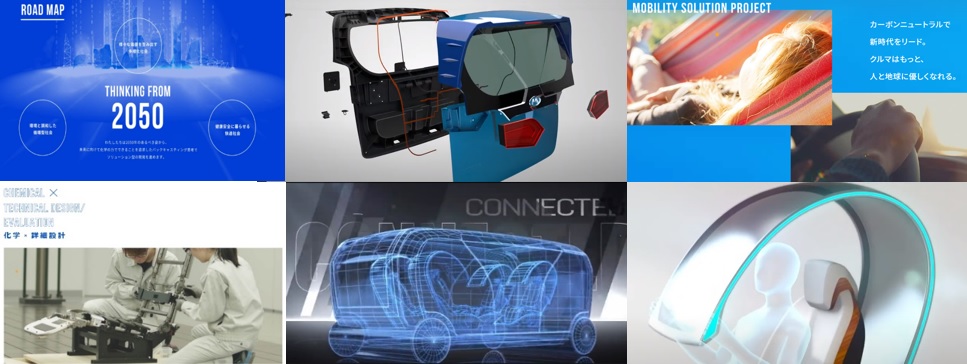[出光興産・人事③](4月1日)▽潤滑油一部主幹部員増田和久▽同部潤滑油企画課長兼潤滑油ビジネスサポートグループリーダー渡邉幸太郎▽同部潤滑油事業管理課長伊藤健司▽同部潤滑油生産技術センター所長兼プロセス開発グループリーダー住友大輔▽同部同センター潤滑油設備管理グループリーダー古澤義博▽潤滑油二部営業研究所機械技術グループリーダー合田隆▽同部東北潤滑油課長黒川隆太▽同部中国潤滑油課長見富健志▽同部九州潤滑油課長小島純▽機能舗装材事業部アスファルト技術課長小松泰幸▽モビリティ戦略室サービス開発担当部長兼開発課長吉野聡▽地域創生事業室次長兼シニア事業開発グループリーダー福島弘之▽総務部断捨離プロジェクト担当部長片島宏二▽デジタル・DTK推進部事業変革課長上原浩一▽情報システム部技術戦略担当部長兼システム技術戦略課長松木敬吾▽同部企画担当部長武藤晃▽同部業務変革四課長兼デジタル・DTK推進部テクノロジー課担当マネジャー吉田朋久▽人事部企画課長吉見英人▽経営企画部企画一課長堀口威▽同部サステナビリティ戦略室長勝山新吾▽同部秘書室長小林創▽ベトナム事業室主幹部員企画渉外担当日下竜司▽同事業室事業構造強化担当部長角田雅文▽同事業室企画渉外課長井上光太郎▽同事業室事業運営課長大西耕▽北海道支店販売一課長周藤伸次郎▽同支店販売二課長田中直岐▽同支店販売三課長原智治▽東北支店副支店長斎藤麻紀▽関東第一支店販売二課長柴崎英司▽同支店販売三課長細井睦弘▽関東第二支店販売企画課長栗原知哉▽同支店販売一課長岩月裕之▽同支店販売三課長鈴木泰輔▽中部支店販売三課長大塚秀樹▽関西支店販売一課長町田憲治▽中国支店販売企画課長漁野彩貴▽北海道製油所副所長兼人事課長吉野晃崇▽千葉事業所人事課長東敏行▽愛知製油所管理課長飯島寛暁▽同製油所業務課長渋谷隆太▽徳山事業所CNX・プロジェクト担当部長具嶋文彦▽同事業所管理課長遠藤司。
出光興産 人事③(2022年4月1日)
2022年3月15日