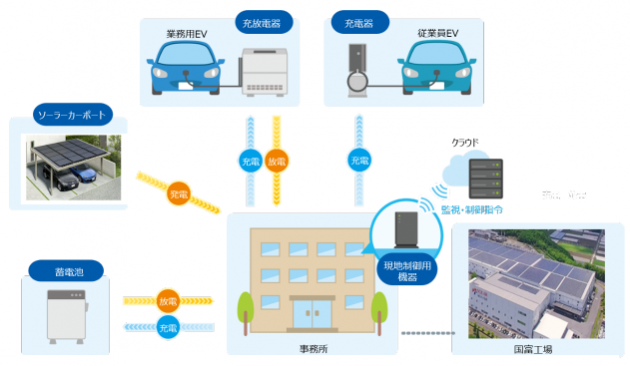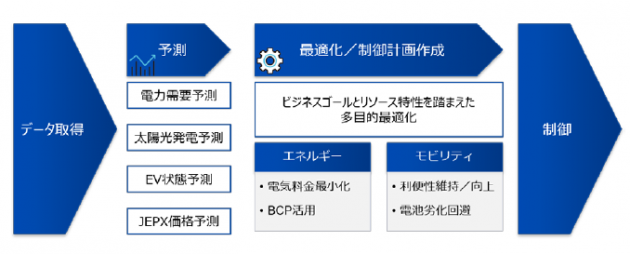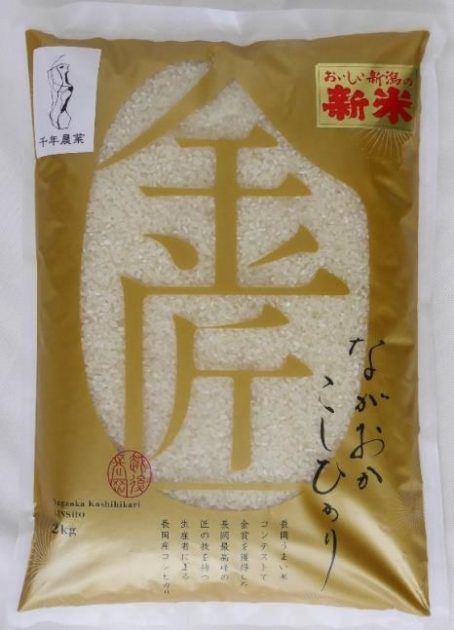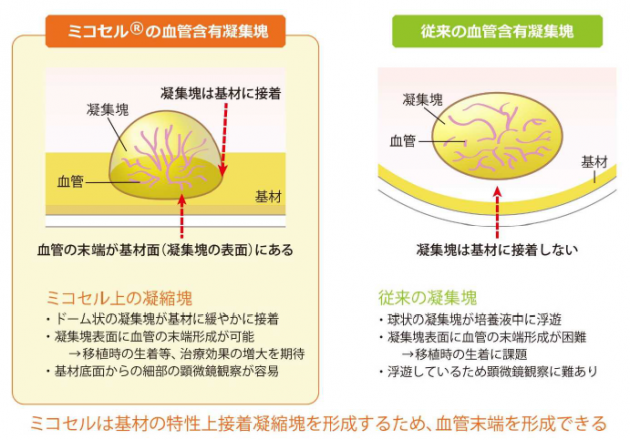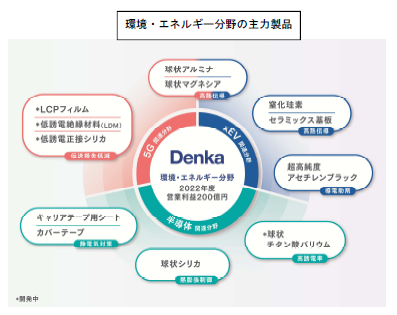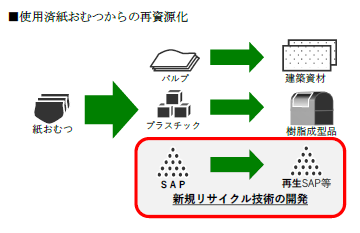富士フイルムはこのほど、子会社のバイオ医薬品開発・製造受託会社(CDMO)フジフイルム・ダイオシンス・バイオテクノロジーズ(FDB)が米国イーライ・リリー社開発の新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)向け抗体医薬品の原薬製造を受託したと発表した。来年4月よりデンマーク拠点で製造を開始し、低中所得国への抗体医薬品の普及に貢献する。
FDBは30年以上の受託実績と高度な生産技術・最新設備をもつバイオ医薬品CDMOで、ホルモン製剤や抗体医薬品、遺伝子治療薬、ワクチンなどあらゆる種類のバイオ医薬品の生産プロセスを開発し、少量生産から大量生産、原薬から製剤・包装までの製造受託に対応する。
同社はビル&メリンダ・ゲイツ財団がウェルカム財団やMastercardとともに4月に立ち上げたCOVID-19治療推進プロジェクトが開発・製造を支援するCOVID-19治療薬のグローバル供給のパートナーとして、デンマーク拠点の一定の製造能力を確保。今回、同プロジェクトとイーライ・リリー社間の抗体医薬品の開発・製造支援合意に従い、FDBは同医薬品の商業生産に必要な原薬の製造を開始する。
FDBのデンマーク拠点は、20kl動物細胞培養タンク6基などの大量生産設備に加え、約1000億円をかけて大型培養タンクの増設、製剤ラインの新設、包装ラインの拡張で原薬の生産能力を倍増する。
同社はCOVID-19ワクチンや治療薬の開発が進展する中、顧客ニーズに合った高品質なバイオ医薬品を迅速かつグローバルに供給し、COVID-19の感染拡大の抑止や流行の終息に貢献していく考えだ。