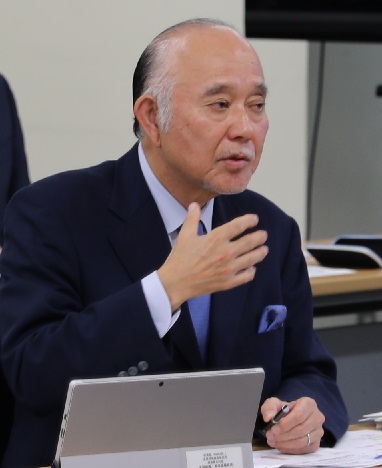独エボニックインダストリーズはこのほど、独バイヤスドルフとCO2を出発原料とするサステナブルな化粧品原料開発の共同研究パートナーシップを結ぶことに合意した。なお、ドイツ連邦教育研究省(BMBF)から約100万ユーロの資金提供を受けている。
革新的で高品質なスキンケア製品を供給しているバイヤスドルフは、カーボンフットプリントを削減できる原料を模索しており、人工光合成は選択肢の1つ。自然界の光合成をモデルに、太陽光エネルギー由来の電力とバクテリアを用いて、水とCO2から原材料を生成するアイデアだ。
バイヤスドルフのシャナー研究開発担当上級副社長は、「両社共同で、製造する原料と応用する製品を見極めていく。このような取り組みは化粧品業界では始まったばかりで、共同研究に参画できたことを誇りに思う」と述べている。
エボニックの人工光合成のハース責任者は、「CO2を出発原料とすることで、自然界の光合成と同様の循環型炭素サイクルが可能となる」とコメント。人工光合成関連の製品群を拡大する機会と捉え、「頼もしいパートナーとともに、サステナブルなCO2由来の製品を含むバリューチェーンを拡大していく」考えだ。
この共同研究は、両社の協業に加え、昨年9月に始動したBMBFのプロジェクト、「パワー・トゥー・エックスⅡ(P2XⅡ)」に参加することを意味する。P2XⅡは、エネルギー転換分野に関するドイツ最大の研究イニシアチブ「コペルニクス・プロジェクト」の1つ。P2XⅡだけで42ものパートナーが参画しており、再生可能エネルギーを活用した高品質な製品を製造するためのプロセス開発を目指している。