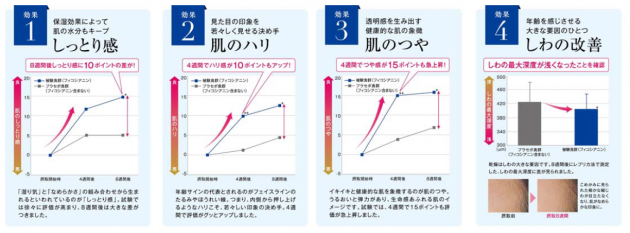DICはこのほど、世界最大級のBOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムメーカーである印Jindal Poly Filmsと、インド国内において機能性CPPフィルムの市場開拓で協業すると発表した。
インド国内では、使い捨てプラの使用規制強化など他国と同様に環境対応や衛生管理面での機能ニーズが高まり、食品包装の分野でも機能性に優れたフィルムが求められている。中でもフィルムの軽量化、モノマテリアル化などに適した機能性の高いCPPフィルムの需要が今後伸びることが見込まれる。
Jindal社は、インド国内市場の成長を見越し、2018年よりCPPフィルム事業に参入。これに際し、DICは協業の提案を受けており、Jindal社との協業はインドのフィルム市場開拓の第一歩となるものと判断し、具体的な検討を進めてきた。
両社は協業内容として、①技術ライセンス契約を締結し、DICの生産パッケージング技術をJindal社に供与、②Jindal社のインド国内工場にて、DICの技術を用いた機能性CPPフィルムを開発・量産化、③合弁会社の設立を視野に、Jindal社が生産した機能性CPPフィルムをインド国内において共同販売、を検討しており、早ければ2021年度中に具体的な活動を開始する予定。
DICはこれまで、日本国内を中心に、フィルムの機能面と環境面の両面から社会に価値を提供してきた。世界的なサステナブルニーズが高まるなか、今回の協業を通じて、日本で培った高度な技術をインド市場に投入してフィルム事業拡大を目指し、将来的にはインド以外の地域においても、協業を拡大することを検討していく。