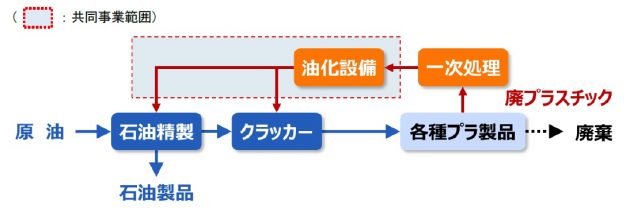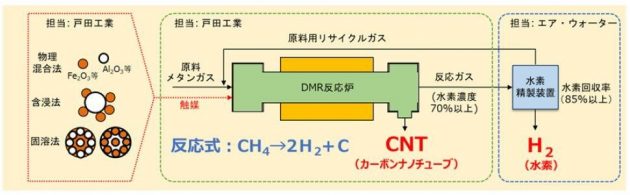JSRは21日、川崎市のキング スカイフロントに建設した新研究所「JSR Bioscience and informatics R&D center(JSR BiRD)」が開所したと発表した。

新研究所では、①ライフサイエンス研究の深掘と社会実装、②インフォマティクスの強化、③オープンイノベーションの3点の施策を通じ新規ビジネスを創出していく。
①については、細菌叢を核にしたライフサイエンス分野の研究を進め、その成果やアイデアを早期に社会実装することを目指す。
②については、インフォマティクスの研究者の活動拠点として、最先端のシミュレーション・深層学習を深耕することで同社の製品開発力を強化していく。新研究所を拠点に、同社グループのインフォマティクスを通じた活動をより活性化し、デジタル変革を本格化して顧客の価値へつなげていく。
③については、オープンイノベーションの拠点として、アカデミアやスタートアップ企業との共同研究で技術の相互補完と強化を図る。通常では交わらない3つの目的をもった研究者達が新研究所では自由闊達に交流し、意見交換しながらイノベーティブに研究開発を行う予定。
同社は、JSR BiRDでの研究開発によって作り上げた製品群が、人々の健康で幸せな生活が可能な社会、安全安心で豊かなデジタル社会、低環境負荷で持続可能な社会に貢献していくことを目指す。