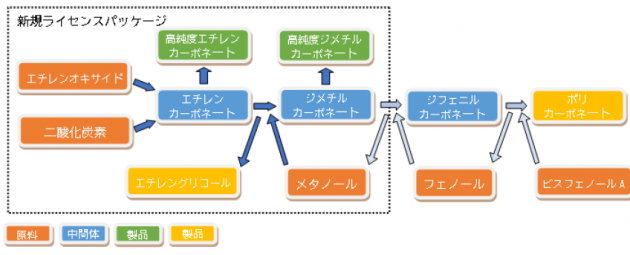DXがキードライバー、デジタル基盤強化に注力
中外製薬は25日、DXメディアセミナーを開催した。同社は今年2月に新成長戦略「TOP I 2030」を発表。「世界最高水準の創薬実現」と「先進的事業モデルの構築」を戦略として掲げ、世界のヘルスケア領域でのトップイノベーターを目指している。キードライバーの1つにDXを設定し、創薬、開発、製薬、バリュー・デリバリーの各フェーズや、それらを支える成長基盤をデジタル技術で改革していく。
昨年3月には「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」打ち出しており、今回、デジタル基盤強化に向けた3つの取り組みを紹介した。1つ目は、今年4月に始動した「Chugai デジタルアカデミー(CDA)」。デジタル人財を体系的に獲得・育成・強化するため、社内育成と社外還元の2つをコンセプトとしている。
社内の育成強化では、全本部から対象人財を募集し、職種共通/職種別専門の講座で構成されるOff-JTと実践的なOJTまで含めた包括的な育成プログラムを提供。また社外還元では、社内で蓄積した「創薬×デジタル」ナレッジを、学生を中心とした次世代人財に積極的に提供し、中外製薬のブランド・採用力強化を図る考えだ。
今年度は、高度解析・統計型のデータサイエンティスト(DS)とデジタルプロジェクトリーダー(DPL)を最優先に設定し、各数十人を育成する。対象人財をアシスタントやJr.エキスパートレベルへ引き上げ、さらに現場に戻って経験を積むことでデジタルプロジェクトを管理するエキスパートレベルを目指す。また、CDAのコンセプトを実現するため、教育コンテンツを提供する様々なパートナー企業との連携も模索していく。
2つ目は、デジタル基盤強化のカギとなる「デジタルイノベーションラボ(DIL)」。ビジネス×デジタル観点による業務改善や新たな価値創造を実現させる仕組みであり、ビジネスとしてだけでなく、チャレンジ精神を醸成するため社員の風土改革としての成果創出も図る。全体像として、アイデアを募集後、中外社員と外部のパートナーを「マッチング」し、企画書(PoC〈概念実証〉計画書)を具体化。その後、2~3カ月でPoCを実施し本番開発を目指す。DILはこれまで2回実施され、全部門の社員から各回とも100件以上のアイデアの応募があり、社内のアイデア実現インフラとして定着しつつある。
3つ目は、「CHUGAI RPA(リコンシダー・プロダクティブ・アプローチ)」。通常RPAはロボットによる自動化と訳されるが、同社は業務見直しとして推進。2018年に取り組みを開始以降、100を超える業務シナリオを自動化し、約7.7万時間以上の業務時間の削減を実現した。RPA市民開発者の社内認定制度を導入するなど、社員のモチベーションの向上を図っている。
ただ、組織によって積極性に濃淡があるなど課題が見えてきたため、今年から新たに再スタート。RPA×AIによって業務変革が当たり前のように行われることで、KPIとして2021年に5万時間以上、2023年には10万時間以上の業務削減を目指す。その達成に向けた取り組みでは、すべてのユニット・本部・コーポレート基本組織がRPA推進活動計画書を作成。2021年は全社で181件のテーマが出てきており、4.3万時間の削減が期待できる。
また、アイデアを集約するプラットフォーム「RPA IDEA BOX」を導入。全社員がアクセス可能となっており、見える化を図ることで、さらなる効率化を狙う。さらに「RPAスクエア」を開校。業務効率化、自動化に関する基礎から応用までの幅広いコンテンツを用意しており、社員のITリテラシーを向上させていく考えだ。