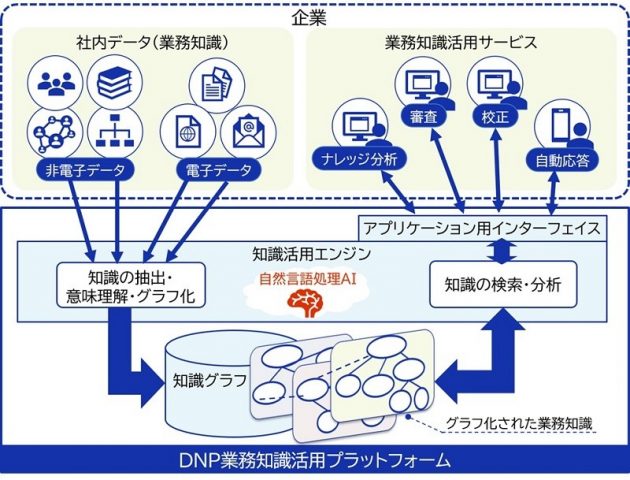三井化学はこのほど、仏エコバディス社(EcoVadis)のサステナビリティ評価で「ゴールド」に格付けされたと発表した。「ゴールド」に格付けされるのは、全評価対象の上位5%の企業。「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つのテーマで包括的に評価が行われ、同社は今回、「環境」と「労働と人権」の両分野で特に高い評価を受けた。3年連続の認定。
三井化学は、SDGsをはじめとする社会課題の解決に向けて企業への要請が高まる中、化学産業が社会の基盤と革新を担う存在であり続けるためには、持続可能な社会に向けて大きな責任あると捉えている。
同社グループは「環境と調和した共生社会」「健康安心な長寿社会」を実現するため、独自の評価指標で環境・社会への貢献度の見える化を推進。具体的には、環境貢献価値「Blue Value」とQOL向上価値「Rose Value」を定義し、それらに沿った製品やサービスの提供をはじめとする社会価値創造の取り組みを深化させている。
今後も、グローバルに存在感のあるサステナブルな企業グループを目指していく考えだ。なお、エコバディス社は、国際的なサステナビリティ規格に基づいた独自基準により団体・企業を評価する、信頼性の高い共同プラットフォームを提供している。これまでに世界160カ国、200業種、6万5000社以上の評価を行っており、約300のグローバル企業がサプライチェーン管理のためにこのプラットフォームを使用している。