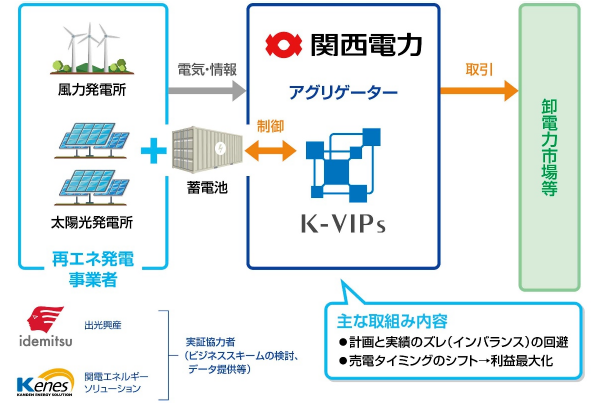ENEOSはこのほど、トヨタ自動車が静岡県裾野市で建設を進める未来技術実証都市、Woven City(ウーブン・シティ)での水素エネルギー利活用について、トヨタと具体的な検討を進めることに基本合意したと発表した。

両社は、トヨタの子会社でソフトウェアを中心とした様々なモビリティの開発を担うウーブン・プラネット・ホールディングスとともに、水素を「つくる」「運ぶ」「使う」という一連のサプライチェーンに関する実証をウーブン・シティおよびその近隣で行い、日本や世界の多くの国が宣言する2050年までのカーボンニュートラル実現への貢献を目指していく考えだ。
ENEOSは、四大都市圏で商用水素ステーションを45カ所展開する水素事業のリーディングカンパニー。本格的な水素の大量消費社会を見据えたCO2フリー水素のサプライチェーン構築や、水素製造に関する技術開発にも取り組んでおり、エネルギーの低炭素化を推進している。
一方、トヨタは、水素を将来の有力なクリーンエネルギーと位置づけており、乗用車から商用車、産業車両、鉄道、船、定置式発電に至るまで様々な用途での水素や燃料電池(FC)技術の開発・普及に取り組んでいる。
こうした両社の水素の知見を生かし、ウーブン・シティを拠点にした様々な実証により、モビリティや人のくらし、そして街全体のカーボンニュートラルを目指すことで、水素を身近に感じてもらいながら、豊かさと持続可能性が両立する社会の実現に挑む。
具体的には、①ENEOSによるウーブン・シティ近隣での水素ステーションの建設・運営②同水素ステーションに設置した水電解装置により再生可能エネルギー由来の水素(グリーン水素)を製造し、ウーブン・シティに供給。トヨタは定置式FC発電機をウーブン・シティ内に設置し、グリーン水素を使用③ウーブン・シティおよびその近隣での物流車両のFC化推進、FC車両を中心とした水素需要の原単位の検証とその需給管理システム構築④ウーブン・シティの敷地内に設置予定の実証拠点での水素供給に関する先端技術研究を行う。