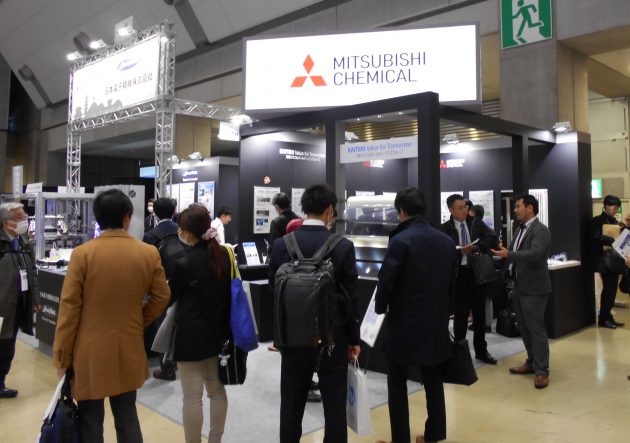
フィルムやシート、紙などの技術と材料、装置が一堂に会する総合展示会「コンバーティングテクノロジー総合展2020」が、先月29~31日に東京ビッグサイトで開催された。その中の構成展「新機能性材料展」と「JFlex」から、化学メーカー4社の展示を紹介する。
三菱ケミカルはエポキシ樹脂の新しい応用として、開発品の高分子エポキシフィルムと伸縮性エポキシフィルムを中心に出展した。いずれも高熱性・高絶縁性などエポキシ樹脂固有の特徴を備えつつ、表面処理不要で様々なインクを塗布・印刷でき、無色透明で低位相差といった優れた光学特性も持っている。さらに、それぞれ高い可撓性と伸縮性があることから、ウエアラブルデバイスやセンサーなどとして活用が見込まれており、そうした製品例を展示していた。
三井化学は機能紙研究会のブースで、ポリオレフィンを噴射生成した多分岐構造の繊維「SWP」を紹介。他素材と組み合わせることで、新たな機能を発現させることができる。最も分かりやすい例は
