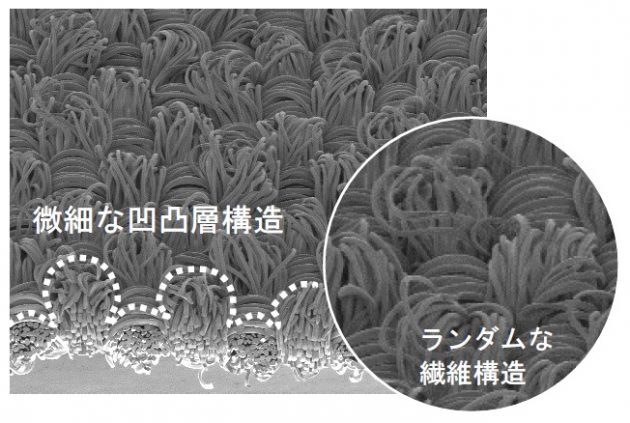三井化学は27日、同社が開発した、ヒトの体温を感知してカラダをやさしく包み込む新素材「HUMOFIT(ヒューモフィット)」が、ワコールから来月に発売されるマタニティ向け新商品「とろけてバストになじむブラ―産後―」に採用されたと発表した。

三井化学の「HUMOFI」は、常温ではゴムのようにしなやかで、曲げ・折り・ひねり・伸ばしのあとでも緩やかに元の形状に戻る「形状記憶性」をもち、加温すると柔らかく冷やすと硬くなる「温度依存性」を併せもつ。ヒトとモノとの接点をもっとやさしく、「ヒトに寄り添う」発想をベースに、同社グループの素材開発と加工技術開発で実現した新素材だ。そのユニークな特性は、医療・介護、スポーツ、アパレルなど様々な用途で高く評価されている。
ワコールの「とろけてバストになじむブラ―産後―」は、授乳前後のバストボリュームの変化に対応し、授乳期から卒乳期、さらに卒乳後も長く使える産後用ブラジャーのコンセプトの下、カップ上辺に「HUMOFI」の特殊シートを搭載した。ヒトの体温に反応してカラダになじむ特殊機能により、バスト変化の大きい産後の胸にジャストフィットするマタニティブラジャーとなっている。