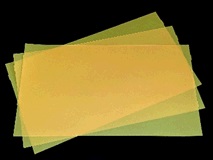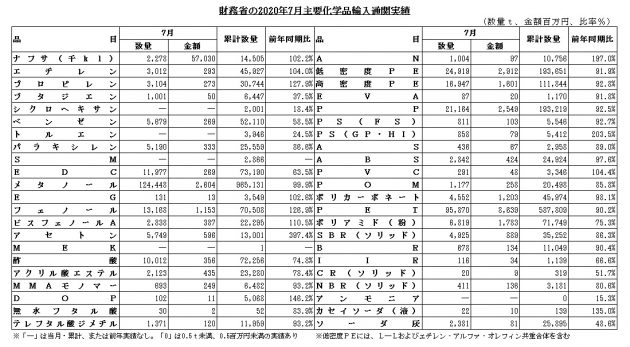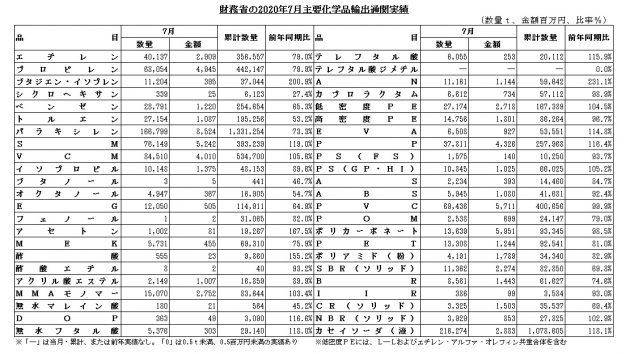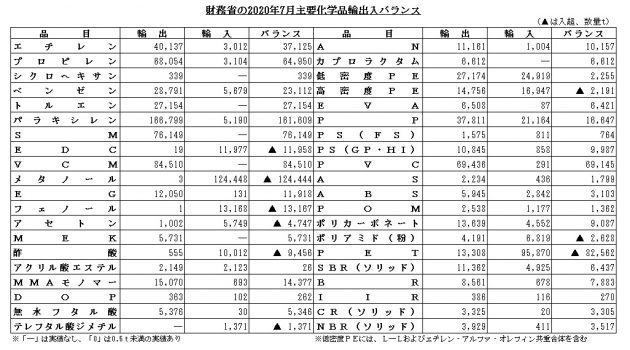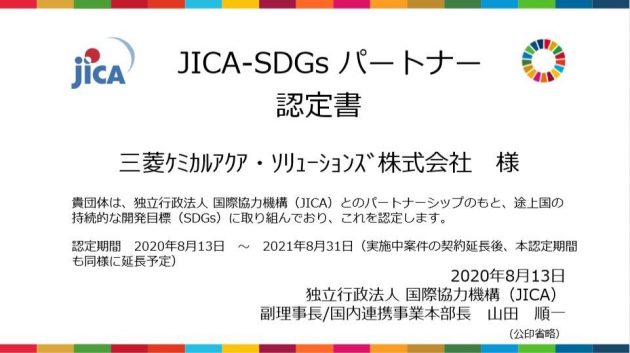ESG経営を推進、〝未来につづく安心〟を創造
積水化学工業は、環境長期ビジョン「SEKISUI環境サステナブルビジョン2050」、および新環境中期計画「SEKISUI環境サステナブルプラン AccelerateⅡ」(2020~2022年度)を策定し、取り組みを開始した。
環境長期ビジョンは、環境に関する多くの問題の顕在化、科学的根拠に基づいた環境課題予測の精度向上などを受け、2050年を見据えた環境課題への取り組みの方向性を再設定。2050年に、〝生物多様性が保全された地球〟を実現することを目指し、製品や事業といった企業活動を通して様々な自然環境および社会環境課題の解決を目指す。
企業活動では地球上の自然資本、社会資本を利用して活動していることを認識し、地球上の課題解決をすることで、自然資本、社会資本のリターンに貢献していく。そのための活動として、「サステナビリティ貢献製品の市場拡大と創出」「環境負荷の低減」「環境の保全」の3つを重視する。従業員1人ひとりが環境課題を認識し課題解決力の高い人材集団となること、そしてあらゆるステークホルダーと連携することにより、これらの活動を加速させていく考えだ。
一方、新環境中計は、長期ビジョンが目指す2050年の姿からバックキャストした中期のマイルストーンを設定し、重要実施項目と目標値を設定した。
①統合指標「SEKISUI環境サステナブルインデックス」による進捗把握は、自然資本に加えて社会資本に対してもその負荷を削減し、貢献が拡大できるようにリタ―ンに努め、業容倍増を目指す2030年には、リターン率100%以上を維持していく。
②「環境貢献製品」制度では、今年度からは「サステナビリティ貢献製品」制度へと進化させ、課題解決の持続可能性を向上させていく。さらに、環境課題解決への高い貢献度と企業および製品の高いサステナビリティをもつ製品を「プレミアムサステナビリティ貢献製品」として選定、戦略的に伸長を後押しする施策を展開していく。
③気候変動課題に対する取り組みでは、脱炭素社会の実現を目指し、2050年に企業活動による温室効果ガス排出量をゼロにする長期目標を設定。2030年には購入電力を100%再生可能エネルギーに転換することを目指す。新中計では「エネルギー調達革新」の段階に移行し、「スマートハイムでんき」や、ESG投資枠400億円の活用などにより、再エネの調達を積極的に推進する。
④資源枯渇課題に対する取り組みでは、2050年のサーキュラーエコノミー実現を目指し、マテリアルへの再資源化をさらに推進。また、廃棄物から微生物の力でエタノールを生産するBR技術の実証事業を行い、ケミカルリサイクル技術の社会実装を図り資源循環を推進していく。さらに、様々な企業、業界団体とのイニシアチブ(CLOMA、JaIMEなど)にも積極的に参加し、企業間の連携した取り組みによって、関連する海洋プラスチック問題などの社会課題解決への貢献を拡大させていく。
⑤水リスク課題に対する取り組みでは、水リスクはローカルな課題であることを認識し、各事業所で取り組みを変えて実施。水資源の維持に対しては、水使用量の多い生産事業所は取水量を10%削減し(2016年度比)、COD(化学的酸素要求量)排出量の多い生産事業所は河川放流水のCOD総量を10%削減する(同)ことを目指す。そして、生産事業所での流域特有の水リスクの把握を行い、課題解決となる取り組みを実行し、水リスクの低減に努めていく考えだ。
同社グループでは、社会の持続可能性向上と同社グループの利益ある成長の両立を目指す〝ESG経営〟を基本戦略とした長期ビジョン「Vision2030」を掲げる。今回、環境長期ビジョンと新環境中計を策定し、ESG経営の中核の1つである環境面から中長期の取り組みの方向性を定めた。これを今後着実に推進することにより、サステナブルな社会の実現に向けて、LIFEの基盤を支え、〝未来につづく安心〟を創造していく方針だ。
SEKISUI環境サステナブルビジョン2050