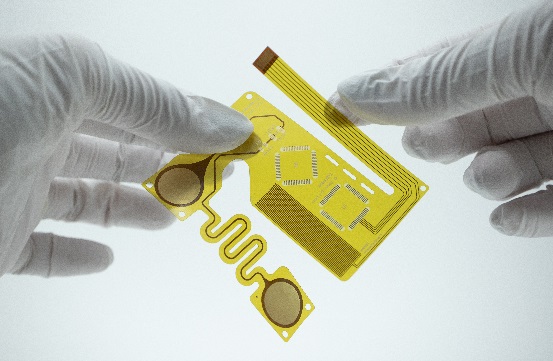三井化学はこのほど、新規熱可塑性ポリウレタン「FORTIMO(フォルティモ)」が、エレコムの最新スマートフォンケース「極み」シリーズに採用されたと発表した。
採用されたのは、iPhone11、Xperia5、Xperia8、Galaxy A20、AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite、AQUOS sense3 basic、Android One S7のスマホケース。経年劣化による黄変を防ぎ、美しい透明感を持続させる特性が高く評価され、今回の製品群への採用となった。
「フォルティモ」は、従来、技術的に難しいとされ実現できなかった「無黄変性」と「高弾性・高耐熱性」を両立し、「耐久性」にも優れる、三井化学が世界で初めて開発したポリウレタンエラストマー。「熱可塑性ポリウレタン」や「熱硬化・注型ポリウレタン」として、自動車用材料や衣料材料、スポーツ用品、高耐久性工業部材などの幅広い用途がある。
同社は今後も、「フォルティモ」を用いて広く社会に貢献する、モビリティやヘルスケア、フード&パッケージングの分野を中心に、用途開発を加速していく。