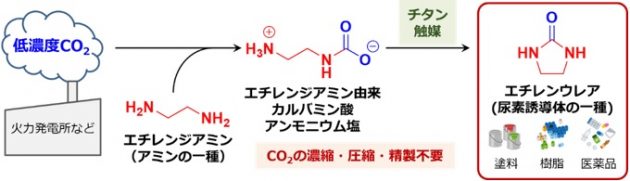[東ソー・人事②](6月25日)▽CSR推進室長平川祐一▽環境保安・品質保証部薬事室長内田淳▽セメント事業室長小川浩▽有機化成品事業部環境薬剤部長岸重美▽高機能材料事業部電池材料部長牛見修▽山形事務所長兼出向東ソー・スペシャリティマテリアル、出向同社伊藤謙一▽技術センター生産技術室長山下明彦▽技術センター四日市分室長築山健一▽南陽事業所環境保安・品質保証部長兼同部(東京)兼南陽認定検査管理組織長兼出向南陽化成小田誠▽南陽事業所化成品製造部長立石裕久▽ファンクショナルポリマー研究所長兼CO2削減・有効利用四日市タスクフォースチーム松本清児▽CO2削減・有効利用戦略室、広報室長松岡克行▽南陽事業所CO2削減・有効利用南陽タスクフォースチーム、同事業所セメント・エネルギー製造部長松村善則▽同事業所ポリマー製造部ペースト塩ビ課長、同事業所ポリマー製造部長堀靖史▽四日市事業所CO2削減・有効利用四日市タスクフォースチーム、同事業所エチレン・エネルギー製造部長中禮誠也▽同事業所同チーム、高分子材料研究所長兼CPパイロット建設チームリーダー阿部成彦▽同事業所CO2削減・有効利用南陽タスクフォースチーム、無機材料研究所長小川宏▽同事業所同チーム、有機材料研究所長木曽浩之▽四日市事業所CO2削減・有効利用四日市タスクフォースチーム、ウレタン研究所長宮田寛▽CO2削減・有効利用戦略室桐木博之▽環境保安・品質保証部薬事室堀江隆一▽出向東ソー・ニッケミ坂本秋彦▽出向和泉産業中野高弘▽技術センターセンター長付藤尾和憲▽環境保安・品質保証部関戸浩明▽南陽事業所総務部勤労課長安増信夫▽経営管理室南陽経理課長土家崇▽南陽事業所環境保安・品質保証部保安管理課長室園忠昭▽同事業所ウレタン第二製造部ウレタン原料第一課長瀧岡大哲▽同事業所同製造部ウレタン原料第二課長山田清▽同事業所CO2削減・有効利用南陽タスクフォースチーム、同事業所セメント・エネルギー製造部セメント課長大草健二▽同事業所CO2削減・有効利用南陽タスクフォースチーム、同事業所セメント・エネルギー製造部動力課長石賀裕輔▽四日市事業所CO2削減・有効利用四日市タスクフォースチーム、同事業所エチレン・エネルギー製造部エチレン課長向井康博▽同事業所同チーム、同事業所エチレン・エネルギー製造部動力課長山口利昭▽秘書室高木謙▽経営管理室小林武明。
東ソー 人事②(6月25日)
2021年6月3日