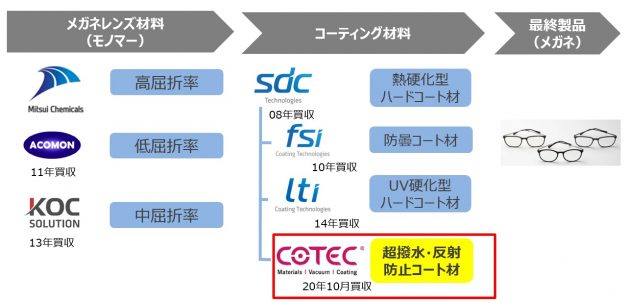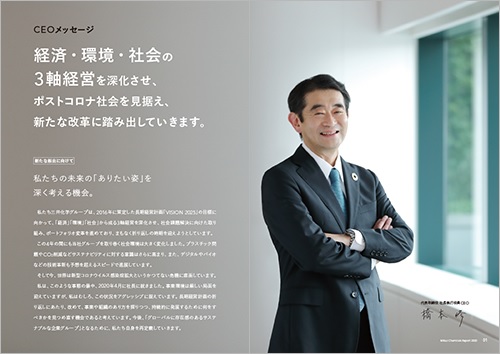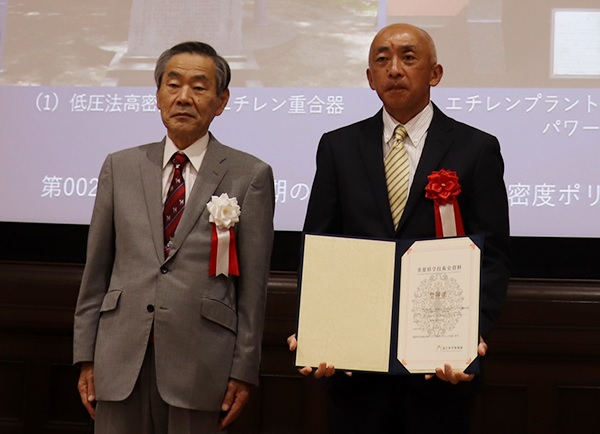三井化学は、三池炭鉱の時代から令和に至るまで100年以上の長きにわたり走り続けてきた、大牟田工場(福岡県大牟田市)の炭鉱電車への感謝の意を込め、未来に向けた〝風景の遺産〟の継承を目的に、このほどメモリアル映像2本をYouTubeなどで公開した。

炭鉱電車は、三井化学専用線(旧三池炭鉱専用鉄道)として濃硝酸や液体塩素といった原材料の運搬などに使用されてきたが、今年5月をもってその運用が廃止された。同社が取り組む「ありがとう炭鉱電車プロジェクト」の中で、炭鉱電車にまつわる映像や音の保存を進めており、今回は大牟田市と荒尾市にまたがり地域と共に歩んだ炭鉱電車の動く最後の姿などを記録として残すため、映画監督の瀬木直貴氏による短編映像2本の制作を行った。
「紅い恋人編」(https://youtu.be/7DdupuFWWNU)では、くれない色の車両が特徴の炭鉱電車と身近に過ごした人々へのインタビューや過去の貴重な映像資料などを通して、炭鉱電車の魅力を掘り起こしている。また、募集したエピソードを基に詩人の道山れいん氏が書き起こした詩の朗読や、〝音の遺産〟としてアーティストSeiho氏が炭鉱電車の音を使って作曲した楽曲が織り込まれた。全編にわたり、炭鉱電車の走行音と、踏切の打鐘式警報機のカランカラン、カランカランというレトロな響きが印象に残る。

「炭鉱電車の1日編」(ttps://youtu.be/H6sZ6VK6xZo)は、炭鉱電車の運行、整備に長く携わってきた人々の1日の仕事を追いかけたドキュメンタリー。運転や整備の様子、機関庫や工場内を走る様子、液体塩素を運ぶ黄色いタンクのラストランなど、貴重な映像を収録している。
制作した2本の映像は、地域の資産として自由に活用してもらうため、先月末、大牟田市をはじめ関係者に同映像の贈呈が行われた。