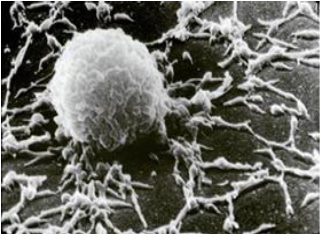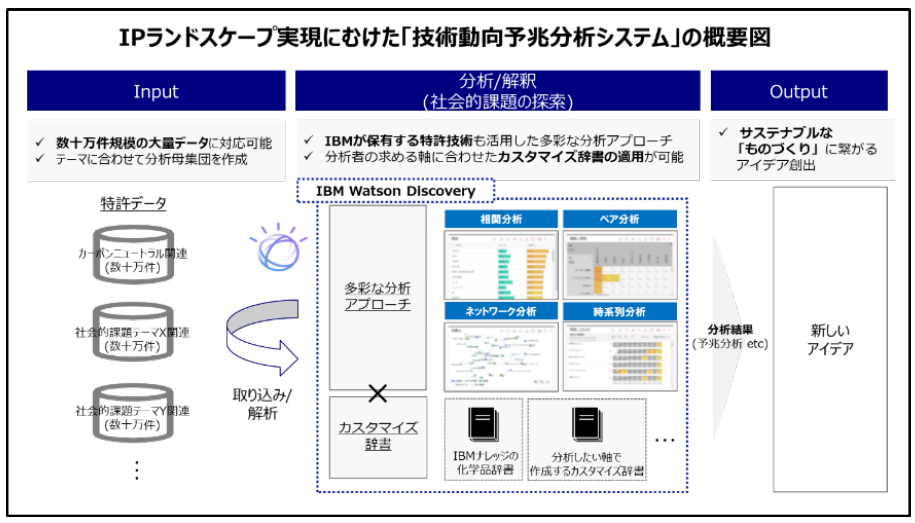宇部興産はこのほど、人工修飾核酸化学技術群を基礎としてより安全かつ効率的な新規核酸医薬品の実用化を目指すルクサナバイオテクへの第3者割当増資の引き受けによる出資を決定したと発表した。
ルクサナバイオテクは、大阪大学大学院薬学研究科(小比賀聡教授)の画期的な人工修飾核酸に関する研究成果を社会実装する目的で、2017年に設立。人工修飾核酸技術のモノマー群(核酸合成物を構成する部品素材)と、これらのモノマー群を核酸合成物に設計する配列デザインノウハウをコア技術としている。これらの技術を基に、核酸医薬品を開発する製薬メーカーとの共同創薬や技術ライセンス提供を実施することで、未だ薬のない病気に対する治療方法を創出することを主事業としている。
今回、宇部興産は、新規核酸医薬品の創薬ニーズに対するルクサナバイオテクの取り組みに賛同し、出資を決定した。ルクサナバイオテクの創薬力に加えて、宇部興産がこれまで培ってきた低分子医薬品原薬受託製造における高い有機合成・プロセス開発力、生産・品質管理力、承認申請力、およびその供給実績を最大限に活用し、今後需要が高まるとされる核酸医薬品の開発推進に取り組んでいく。
宇部興産の医薬事業は、技術革新にあふれた「クスリづくり」を地域から発信し、すべての人々の健康に貢献することを目指している。これからも医療に貢献するため、自社/共同研究開発による「創薬」と「原薬・中間体製造」を両輪として新しい医薬品の種となる化合物を創出していく。