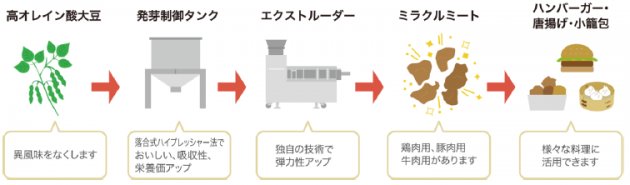業界の垣根を超える24社により「量子技術による新産業創出協議会」が9月1日に設立され、記念シンポジウムが開催された。発起人はJSR、第一生命ホールディングス、東京海上ホールディングス、東芝、トヨタ自動車、日本電気、日本電信電話、日立製作所、富士通、みずほフィナンシャルグループ、三菱ケミカル(順不同)の11社で、現在24社が参画している。
来るべき量子時代に向けて量子関連分野の新産業を創出することを目的とし、科学技術の発展への貢献を通じた産業の振興と国際競争力の強化により、国民の安全・安心な暮らしや社会の確立を目指す。
現在進行するDX(デジタルトランスフォーメーション)は、近い将来、量子(Quantum)技術に基づくQX(クオンタムトランスフォーメーション)に進化する。それに向け、情報通信技術(量子コンピューティング、量子暗号通信)、関連基盤技術(材料、デバイス)、重要応用領域(量子マテリアル、量子生命・医療、量子バイオ、量子センサ、量子AIなど)や人材、制度・ルールに関する課題を検討し、四つの部会でユースケースを創出する。
「量子波動・量子確率論応用部会」では、まず金融価格・リスク分析に向けたゲート型量子コンピュータの開発を進め、「量子重ね合わせ応用部会」では、システムの品質やセキュリティの検査、材料開発や創薬への有効性を検討する。
「最適化・組み合わせ問題に関する部会」では、イジングマシンで製造コスト削減や医薬探索、金融ポートフォリオの最適化などを進め、「量子記号・量子通信部会」では、銀行間決済や証券取引、金融・医療情報基盤、SCADA(産業情報の一元管理)ネットワーク、高セキュリティ通信などへの展開を検証していく。
シンポジウムでは、9月1日に発足したデジタル庁から赤石浩一デジタル審議官が演壇に立ち、「現実・仮想空間が高度に融合したシステムで新たな価値を創出する、人間中心の社会、Society5.0を目指す。そのために政策からルール、ツール、データ、インフラ、利活用環境までを包括したデータ戦略を前倒しで進める」と述べた。
また東京大学の五神真教授は、「リアルタイムデータを活用し、仮想・現実両方の地球規模の課題の解決を目指す」とし、急展開する量子技術に対し、オールジャパンの研究開発体制の確立と早期社会実装に向け、2台の量子コンピュータを導入した「量子イノベーションイニシアティブ協議会」にも触れた。
一方、今回発足した協議会の島田太郎実行委員会委員長(東芝執行役上席常務)は、「世界のあらゆる団体と様々なテーマで積極的につながり、量子産業を創出する」として、企業、アカデミアなどその規模を問わず、多くの参加を呼び掛けた。