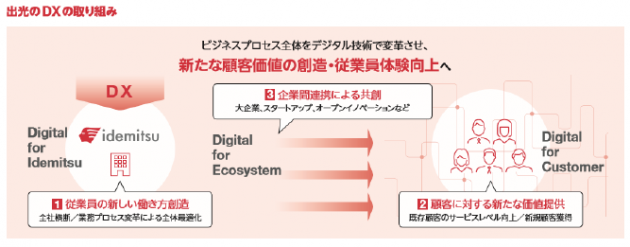花王はこのほど、「大丸有(東京都の大手町、丸の内、有楽町)エリアにおける動静脈一体物流による効率的なプラスチック循環に向けた実証事業」に参画すると発表した。
東京都の「再生利用指定制度」によって生産者から消費者への「動脈」と消費者から生産者への「静脈」の一体物流を実現し、廃棄物の回収・圧縮保管・リペレット・製品化までの一連のプロセスを通して、プラスチック資源循環の課題の抽出と、ライフサイクル全体での環境負荷・コストの評価を行う。その中で、同社は再生ペレットの物性評価と、日用品包装容器への活用検討を行う。
使用後に適正に回収・再利用されない「プラスチックごみ」は社会課題であり、プラスチック廃棄物をリサイクルするプラスチック循環システムの構築が求められている。一度市場に出た資源(PCR材:ポストコンシューマーリサイクル材)を原材料として再活用する場合、PCR材は組成が様々で発生量も一様でないため、品質が安定せず回収コストもかさみ、継続的に活用する上での課題となる。
今回、三菱地所が丸ビルと新丸ビルのアパレルテナントから排出されるプラスチック製フィルムを分別・計量・保管し、東京納品代行が納品時の帰り便で回収し、センコー商事が異物確認後に圧縮保管。エンビプロ・ホールディングスが破砕・溶融して原材料化(リペレット)し、花王が日用品包装容器の原材料として仕入れる流れだ。
双日、レコテック、日商エレクトロニクスとNTTコミュニケーションズが再生資源プラットフォーム「Material Pool System」を基に、プラスチック循環システム構築に必要なプラットフォームとしての課題を抽出し、東京大学とトーマツが廃プラスチックの収集・運搬プロセスの環境負荷とコストの評価を行う。
花王は昨年から、川崎市の「サーキュラーエコノミー都市実現に向けた低炭素型マテリアルリサイクルモデル構築調査事業」でも、商業施設から回収したPCR材のリサイクルに取り組んでいる。これらのプロジェクトを通じ、プラスチックに関する研究技術を提供することにより、自治体・他企業と連携してプラスチック循環社会実現に貢献していく考えだ。