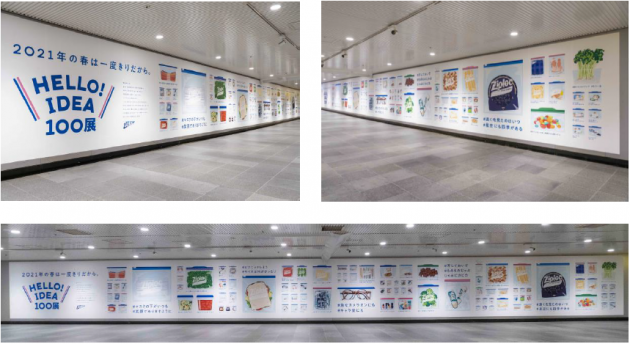皆さんが社会への第一歩を無事に踏み出すことができたのは、皆さん自身の日々の努力は勿論のこと、生まれてから今日に至る家族や親族の支えがあったからこそだ。今まで世話になり育てくれた方々への感謝の気持ちを忘れてはいけない。感謝の気持ちは社会の基本なので、忘れないように。
皆さんには今日から実践してほしい3つのお願いがある。1つ目は「夢をもち続ける」こと。皆さんが宣言した「ゼオンで叶えたい夢」は、若者らしくチャレンジ精神に富んだ素晴らしい夢で、大変頼もしく思う。「夢やありたい姿を真剣に追い求めるとすべてが変わる」ので、夢をもち続け、夢の実現に向け真剣にチャレンジし続けてほしい。
2つ目は「会社を変える、ゼオンを変える」こと。事業環境は凄まじい勢いで変化し、顧客の真のニーズや価値観は多様化し、的確に把握することが難しくなってきた。仕事のやり方・考え方を大きく変えないと生き残れないという強い危機感がある。新しい価値を生み出す土台として、会社と社員のエンゲージメントを強化し、ダイバーシティ&インクルージョンをより深く浸透させていく。皆さんの力でゼオンを変えてほしい。
まずは配属先の上司や先輩から仕事を教わるが、ゼロベースで「本当にこの仕事が必要なのか」「こうやったほうがいいのではないか」あるいは「もっと効率的にできるのではないか」などの視点で提案し、ゼオンを変える。そういう気持ちで挑んでもらいたい。
三つ目は「健康であり続ける」こと。健康は当たり前ではない。朝起きて元気な体で会社に来て、いろいろなことに集中し挑戦して1日が終わることは、会社にとって非常に重要だ。これからも病気にならない、怪我をしないと心に決め、全員が現状より一歩でも健康になるよう鍛錬を重ねて、定年まで元気に仕事をしてほしい。以上、夢をもち続けること、会社を変える・ゼオンを変えるんだということ、健康であり続けること、の3点をお願いする。