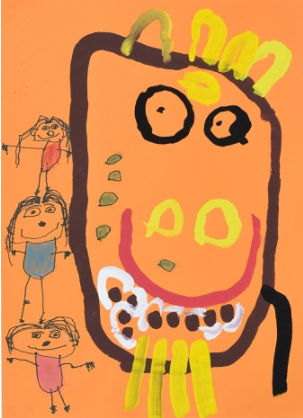デンカはこのほど、主要グループ会社デンカリノテック(東京都中央区)が熊本県高森町、KYOTO,S 3D STUDIO、Wee-vaの4者間で3D計測・診断技術導入による新サービスの開発・提供を目的とした業務提携協定を締結したと発表した。

最先端の3D技術を基軸に、高森町の歴史的文化財を含む建築構造物や鉄道車両などの保全・保護のほか、町の伝統行事のアーカイブや観光事業振興などの業務の効率化につながる新たなサービスの創出を目指す。
デンカリノテックは、コンクリート構造物の調査・診断を通じた最適な補修・補強を手掛けており、360度3Dデジタル計測により建築構造物を線画化し、精度の高い設計・施工から維持管理まで応用展開している。図面や設計図がない構造物にも適用できるため、文化財保全の一環として、世界文化遺産の京都醍醐寺の3D計測を昨年実施した。
デンカグループは経営計画「Denka Value-Up」で、高付加価値インフラ事業をヘルスケア、環境・エネルギーに並ぶ重点分野と位置付けている。デンカリノテックの3D計測・調査診断技術とデンカの特殊混和材などの無機材料を組み合わせて、高付加価値インフラでの事業拡大につなげていく。