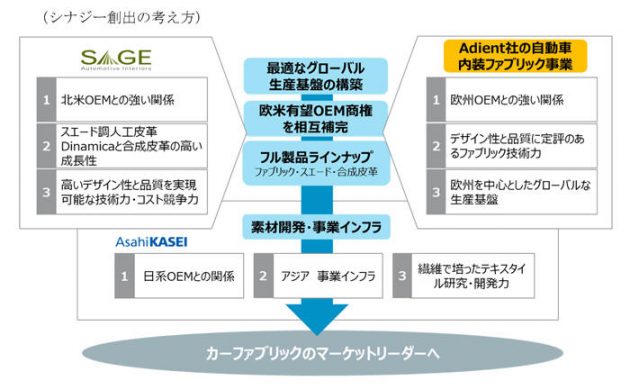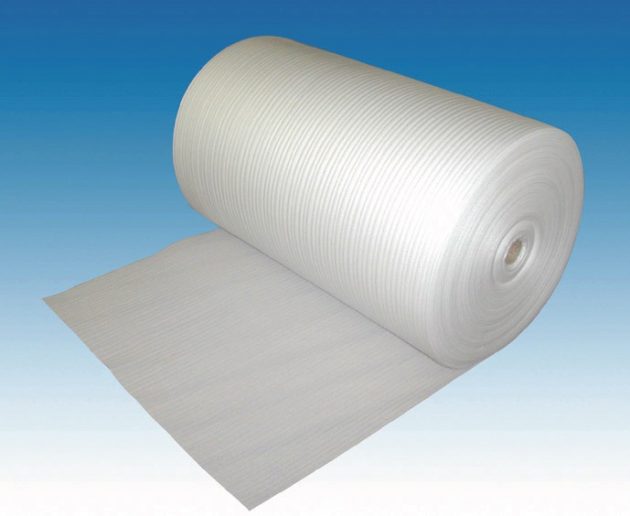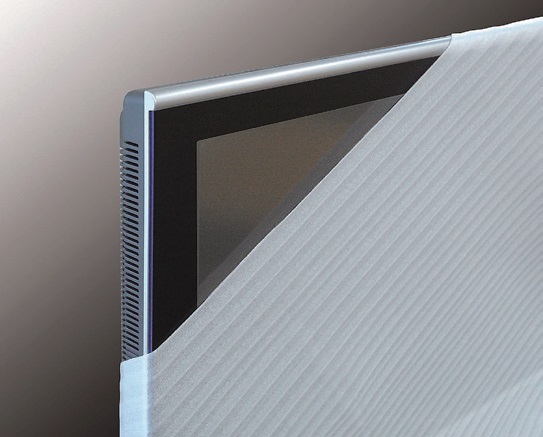旭化成は6日、スチレン系樹脂であるAS樹脂・ABS樹脂・ACS樹脂(製品名「スタイラック」「エステロイ」)事業からの撤退を決定したと発表した。2021年3月末をもって川崎製造所(神奈川県川崎市)内のAS工場を停止し、営業活動も終了する。
同社のスチレン系樹脂事業は、1962年の川崎工場(現・川崎製造所)でのAS樹脂工場稼働から始まり、1964年にABS樹脂工場稼働(1978年に停止し水島工場に統合)、1995年にはACS樹脂事業を開始し現在に至っている。これまで約58年間にわたり、OA・家電・自動車・雑貨用途などに向け国内外の顧客へ製品を提供してきた。
また、2015年には、国内市場の大幅な需要減などによる事業損益の悪化を受け、1967年に製造を開始した水島製造所のABS樹脂工場を閉鎖し、事業構造の改善を図ってきた。
しかしながら、グローバルABS市場で同社製品の優位性を発揮することは容易ではなく、将来的に拡大戦略を描くことも難しいとの判断から事業撤退を決めた。
同社は、中期経営計画「Cs+ for Tomorrow 2021」の中で、経営資源の優先投入や再配分を進めることで事業ポートフォリオの転換を図り、サステナブルで高付加価値な事業体となることを目指している。今後は同事業の経営資源を他の注力事業へと振り向けていく考えだ。