横浜ゴムと産業技術総合研究所(産総研)の共同研究「サステナブル資源を用いたゴム材料の研究開発」がこのほど、第34回日本ゴム協会賞を受賞した。
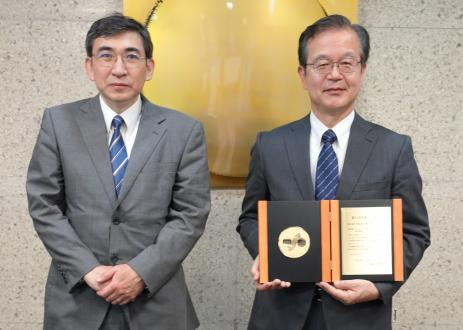
同賞はゴムとその周辺領域における科学・技術、産業分野の発展に寄与し、業績が極めて顕著なゴム協会会員に授与されるもの。今回の受賞は、NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の委託「超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクト」での6年間の研究成果だ。
タイヤ用ゴムを
2022年7月8日
2022年7月7日
2022年7月7日
2022年7月6日
2022年7月6日
2022年7月6日
2022年7月6日
2022年7月5日
2022年7月5日
2022年7月5日