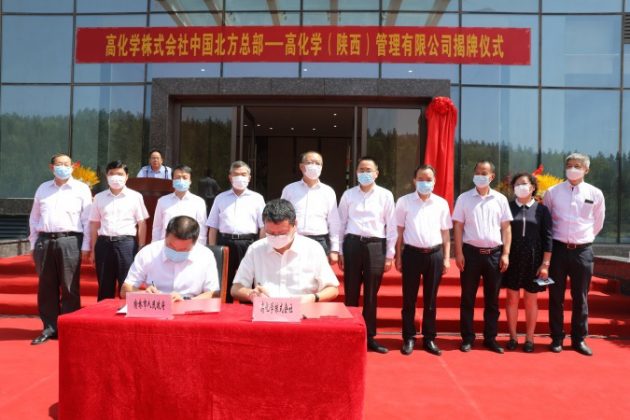三井化学は4日、同社のフレキシブル・高感度・極細の接触・振動センシング基材「PIEZOLA(ピエゾラ)」と、リトルソフトウェア社(東京都港区)の「HuMAN Affective AIプラットフォーム」を融合し、7つの感情を可視化するシステム「PIEZOLA Emotion(エモーション)アプリ」を開発したと発表した。

心電計などの測定器を装着することなく、椅子の上のマットに搭載した「ピエゾラ」が、座るだけで心拍数や呼吸数、体動値といったバイタル信号を検出。リトルソフトウェア社のAIプラットフォームを介し各種バイタル信号を感性に変換することで、「平常心、リラックス、ストレス(超集中状態)、イライラ、ポジティブ、ネガティブ、集中」の7つの感情状態をスマホ画面上に可視化する。

三井化学は、同アプリをヘルスケアや化粧品、自動車、スポーツ、玩具、食品、アミューズメント、レジャー、教育、広告、マスメディア、eスポーツなどの業界に対し、アンケート(主観)だけではわからない、利用者の心理状態を読み解くツールとしてのソリューション情報サービスを提案していく考えだ。
今月6~8日に東京ビッグサイト・南3ホールで開催される「センサエキスポジャパン2021」に、「ピエゾラ」と今回開発したアプリを出展(ブース番号:S-26)。併せて、100℃超の環境下で作動する「ピエゾラ耐熱グレード」、小型・薄型・立体型の電子回路埋設部品の作製を可能にする電子機器モジュール「Eecomid(イーコミッド)」など、新規開発品の出展も予定している。