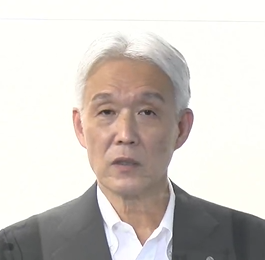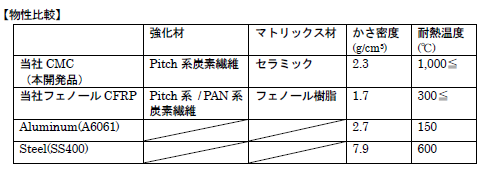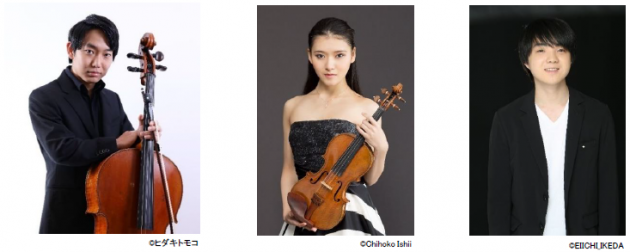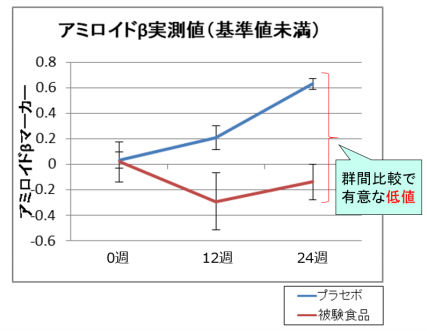脱プラから「改プラ」へ、新造形テーマに開催
三井化学の組織横断的なオープン・ラボラトリー活動「そざいの魅力ラボ(MOLp:モル)」は先週、5日間の期間限定で素材の魅力を体験できる「モルカフェ2021」を開催した。約3年半ぶりとなる3回目。同活動は、いわば部活動のようなもので、有志メンバーが集まり、様々な素材の中に眠っている機能的価値や感性的な魅力を、あらゆる感覚を駆使して再発見し、そこから生まれたアイデアやヒントを社会とシェアしていくもの。

2015年に活動を開始した。当初から同活動のクリエイティブパートナーを務めるエムテド(MTDO)の田子學さんは、回を重ねるごとにクオリティを高めていく活動の源泉に「モチベーション」を挙げる。1回目はプロトタイプの発表にとどまったものの、2回目では製品化までこぎつけた。またその取り組みが、アパレルブランド・アンリアレイジのデザイナー森永邦彦氏の目に留まり、その後、アンリアレイジとイタリアのファッションブランド・フェンディの、「2020-21年秋冬ミラノコレクション」でのコラボというビッグビジネスにつながっていった。3回目となる今回のテーマは「ネオプラスティシズム(新造形主義)」。海洋プラごみ問題をはじめプラスチックに注目が集まる今、持続可能な循環型社会に向けてどうプラスチックを変化させていくのか、脱プラから「改プラ」への可能性を探索し提案した。
会場となったライトボックススタジオ青山(東京都港区)でひと際目を引く、500kg容量の鼠色のフレコンバッグ。樹脂ペレット原料などの保管や輸送に使われるが、耐用年数は15年ほど。使用後も80~90%の強度が残っていることから、そのロングライフ性を生かしてトートバッグや財布へとアップサイクルし製品化した。今回の試みでは、15年後の再利用を前提にフレコンそのもののデザインを刷新、どの部分を使っても見栄えのする仕様に変えた。

会場には様々な素材や製品が、壁に掛けられた説明パネルとともに並ぶが、記者が注目したのは「GoTouch(ゴトウチ)コンパウンド」だ。木粉(和歌山県新宮市)やソバ殻(長野県千曲市)、緑茶殻(三重県松阪市)、ぶどう果皮と種子(山梨県甲府市・笛吹市)といった日本各地の未利用バイオマスを有効活用し、ベース樹脂のポリプロピレンとコンパウンドしたもの。会場では15種類のコンパウンドペレットとその成型品のトレーが展示されていた。混ぜ込む植物性原料の香りや色、質感が楽しめる製品が「ご当地」感を醸し出している。

「三井化学のコア技術とベンチャーのトルムスイニシエイトのペレット化技術で『混ぜる』可能性を追求した」と話す、この取り組みを手掛けた藤本恵造さん。三井化学の誇る相溶化・分散技術を基にした添加剤により、バイオマス混合率50%のコンパウンドが実現。混合率70%以上も可能だという。大半が焼却処理される未利用バイオマスを有効活用することで、CO2の固定化にも寄与する。各地域のロスを減らし化石資源の使用量削減につながるだけでなく、ご当地の魅力と特色を生かしたプラスチックで地方創生の可能性も秘める。藤本さんは「土地ごとの素材で、愛着をもって長く使ってもらえる製品を提供していきたい」と抱負を語る。今後もラインアップを増やし、「ゴトウチ」プラを広く展開していきたい考えだ。
記者的には丹波篠山の栗のイガや鬼皮、紀州の梅の種、酒どころの酒粕、米どころの稲わら、トウモロコシの芯なども面白い。違った視点をもった人とのつながりにより、さらに新たな展開も期待される。「モルカフェ」の取り組み自体がサーキュラー、循環しているようだ。