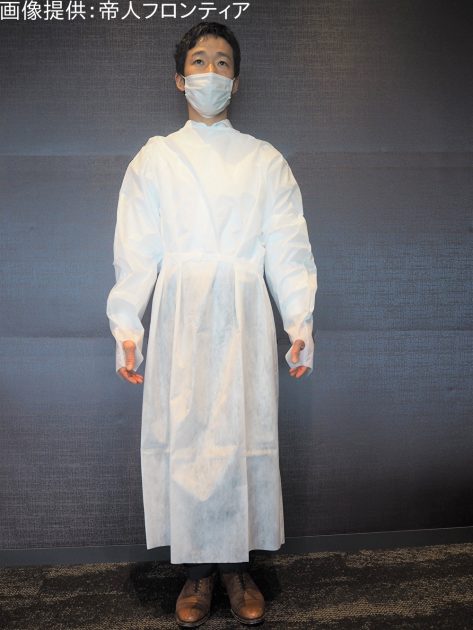東洋紡はこのほど、中空糸型正浸透膜(FO膜)搭載の環境配慮型水処理システムを海水淡水化分野のコンサルタント会社SWPC社(アラブ首長国連邦、アブダビ)と東洋紡連結子会社のアラビアンジャパニーズメンブレンカンパニー(AJMC)と共同で開発し米国へ特許を仮出願したと発表した。今後、実証実験を重ね早期の実用化を目指す。
 中空糸型正浸透(FO)膜
中空糸型正浸透(FO)膜
雨水や地下水に乏しい中東地域などでは、海水から淡水を作る海水淡水化プラントが多く稼働し、東洋紡グループ製の中空糸型逆浸透膜(RO膜)は1日あたり約160万t、約640万人分の使用量に相当する真水を作っている。しかしRO膜法の海水淡水化プラントからは高濃度の濃縮海水が排出されるため、濃縮海水の効率的な処理方法が求められている。
今回、FO膜モジュールを併用して濃縮海水排水量を削減し、システム内で発生するエネルギーを利用する次世代の環境配慮型の水処理システムを開発した。
まず、海水をRO膜で高圧処理して大部分の塩分を除去し濃縮海水と淡水に分け、さらに淡水をRO膜で低圧処理して真水と低濃度塩水に分ける。次に低濃度塩水と濃縮海水を同システム内でFO膜を隔てて接触させると、浸透圧差で低濃度塩水側から濃縮海水側に水流が発生し、濃縮海水は希釈されると同時に、この水流エネルギーをプラント内の圧力ポンプなどの動力として利用する。ここで希釈された濃縮海水は、通常の海水と濃度が変わらないため、RO膜での淡水化に循環利用できる。
通常くみ上げた海水は、化学薬品を使って微粒子を除去するが、濃縮海水を再利用できるためこの工程を省略でき、薬品使用コストも削減できる。このシステムは、既存の海水淡水化プラントにも容易に追加設置でき、濃縮海水の排水量削減と、発生エネルギーでエネルギーの一部をまかなえるなど、大きな設備投資なしに環境に配慮した水処理システムを実現できる。
今後両社と協働で実証実験を行い、安定運転のノウハウなどを確立して早期の実用化を目指す。同システムの普及により、環境負荷が低く、コストを抑えた海水淡水化プラントの運用を支援し、世界の水不足という課題の解決に貢献していく考えだ。