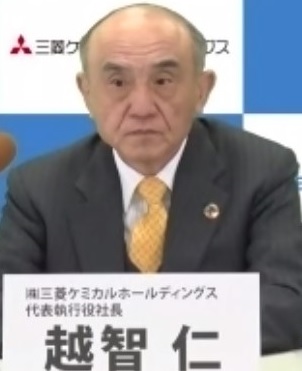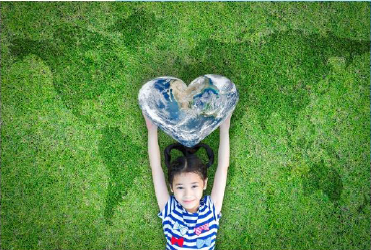帝人は2日、AEV社(オーストラリア)と共同で、ポリカーボネート(PC)樹脂製の近未来モビリティ向けソーラールーフを開発したと発表した。

近未来のモビリティ像としてCASEやMaaSが示される中、世界各国で自動車の電動化や自動運転化に向けた技術開発が進む。また、世界的な指標として、エネルギー効率を総合的に評価する「ウェル・トゥ・ホイール ゼロエミッション」が掲げられるなど、自動車社会にはさらに大きな変化の到来が予測されている。
こうした中、両社は、将来のEVに求められる技術基盤を獲得・整備するため、2019年よりLS-EV(低速EV)の共同開発を推進。最近の成果として、用途に合わせた車体を搭載して自動走行が可能な多目的プラットフォーム「ブランク・ロボット」を開発した。
今回開発したLS-EV向けソーラールーフは、帝人のPC樹脂「パンライト」グレージングを表層に使い太陽電池を搭載。帝人が長年培ってきたグレージングの知見を駆使し、ガラスでは難しい車体ルーフに適した曲面形状を一体成形することで強度や剛性を実現した。また、PC樹脂の課題であるは耐候性についても、帝人独自のハードコート技術を活用することで自動車に要求される10年相当の耐久性を実現した。

一方、ソーラ―ルーフに搭載した太陽電池セルの出力は、豪州でのテストで一般的なソーラーパネルと同等の約330Wを記録。さらに、両社はソーラールーフのエネルギー効率を実証するため、一般車両向けLS-EVを想定した10kWhのバッテリー搭載のプロトタイプ車体を製作。「ブランク・ロボット」に装填して試験を行ったところ、走行距離が30~55Km(最大約30%)伸びることが確認された。
両社は今後、各部品に帝人の素材や技術を活用した量産向け軽量LS-EVについて、2022年後半の実用化を目指し、ソーラールーフの技術向上を図りながら、「ウェル・トゥ・ホイール ゼロエミッション」の実現に向けた取り組みを進めていく。
帝人は、AEV社との取り組みを一層強化していくことにより、近未来のモビリティへのニーズを先取りし、自社の高機能素材や設計、デザイン、複合化技術による技術提案力を強化していく考えだ。