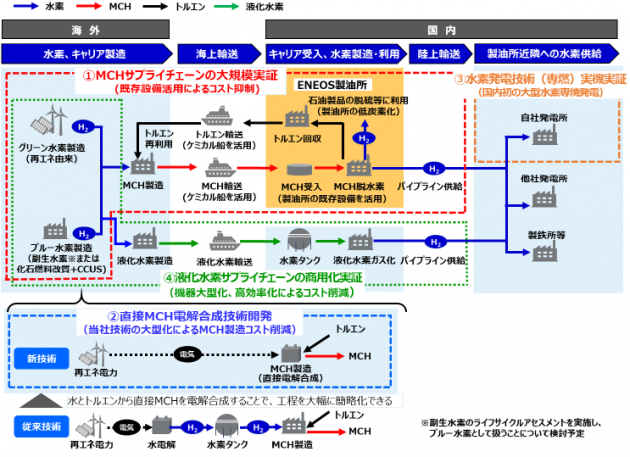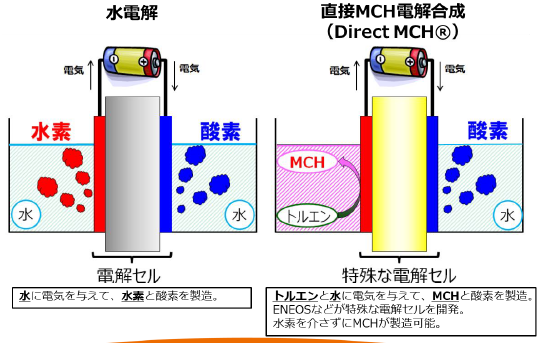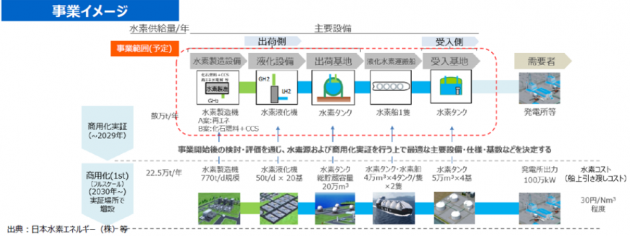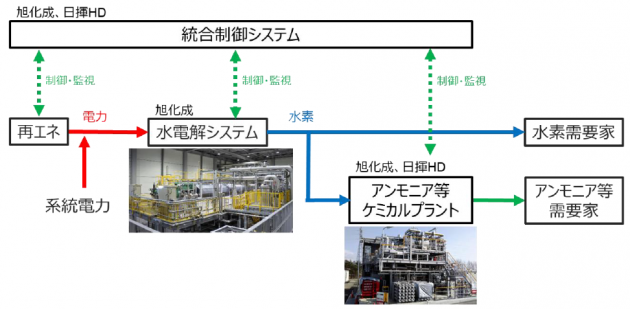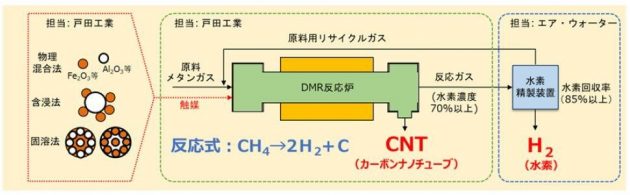NEDOグリーンイノベーション基金事業に採択
山梨県、東レ、東京電力ホールディングス、東京電力エナジーパートナー、日立造船、シーメンス・エナジー、加地テック、三浦工業、ニチコンは1日、コンソーシアム「やまなし・ハイドロジェン・エネルギー・ソサエティ(H2-YES)」を構成し、大規模P2G(Power to Gas)システムによるエネルギー需要転換・利用技術開発に係る事業を開始すると発表した。なお、同プロジェクトは、グリーンイノベーション基金事業における新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業の採択を受けている。
同日オンラインで開催した共同記者会見の中で、山梨県の長崎幸太郎知事は「再生可能エネルギー導入拡大と、GHG(温室効果ガス)削減は人類共通の課題であり、化石燃料からの脱却が必要だ。山梨県、東レ、東電はこれまで、米倉山(こめくらやま、甲府市)において再エネでグリーン水素を製造するP2Gシステムの開発を進め、基盤技術を確立してきた。しかし