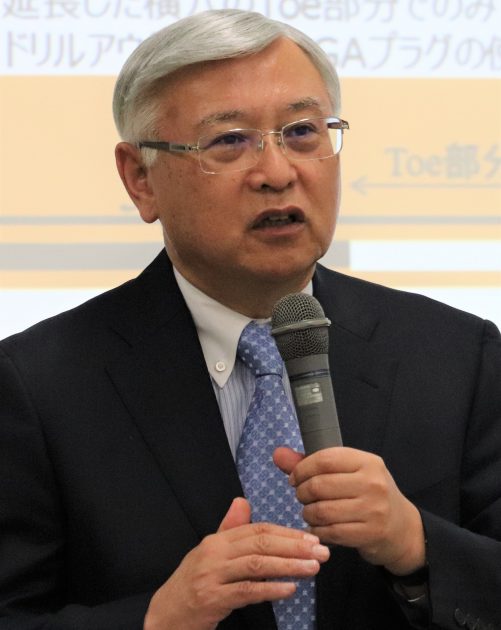一歩先のソリューション提案、開発力を上げるモビリティ戦略
━EV化が進む自動車業界の現状をどう見ていますか。
 佐藤 ハイブリッドを含めた電動化はどんどん進むだろうと見ています。ただ「Pure EV」は、普通の経済効果だけでは進むのに相当時間がかかるでしょう。電池の性能やインフラの問題もあるし、「Well-to-Wheel」の考え方から、全体としてEVが環境に良いとなってくるには、技術も社会も変わっていかなければいけない。
佐藤 ハイブリッドを含めた電動化はどんどん進むだろうと見ています。ただ「Pure EV」は、普通の経済効果だけでは進むのに相当時間がかかるでしょう。電池の性能やインフラの問題もあるし、「Well-to-Wheel」の考え方から、全体としてEVが環境に良いとなってくるには、技術も社会も変わっていかなければいけない。
2030年までの「Pure EV」普及率について様々な数字がありますが、おおむね10%程度です。そんな中で、例えば中国は国策的にEV化をやるという動きに出ている。そこには目先の環境問題もあるでしょうが、内燃機関がなくなることで圧倒的に技術的なキャッチアップがしやすいといった考えがあると思います。
エンジンの開発・制御といった最大の技術ハードルがなくなることで、新規参入者にとっては、西欧あるいは日本をキャッチアップするときに、有利な舞台になっていく。その意味でもEV化は進んでいくだろうと思います。
━EV化が御社のビジネスに与える影響は。
佐藤 現在、燃料タンクに使われる接着性ポリオレフィン「アドマー」、ギアオイルの添加剤「ルーカント」などがありますが、エンジンが小さくなっていき、最終的になくなってしまえば需要としては減っていく傾向だと思います。しかし、内燃機関が完全になくなるまでには時間がかかるでしょうから、まだまだ息は長いと思っています。
一方、モーターに替わることでバッテリーは大きくなる。バッテリー材料を本格的にやっている他社に比べると、当社のビジネスは、まだこれからだと思っていますが、それでもLIBのセパレータに使う超高分子量ポリエチレン「ハイゼックスミリオン」、あるいは電気系統で求められる耐熱のプラスチックなどを開発しており、トータルではプラスになってくると思います。
━注力しているPPコンパウンドの今後の戦略について。
佐藤 PPコンパウンドは