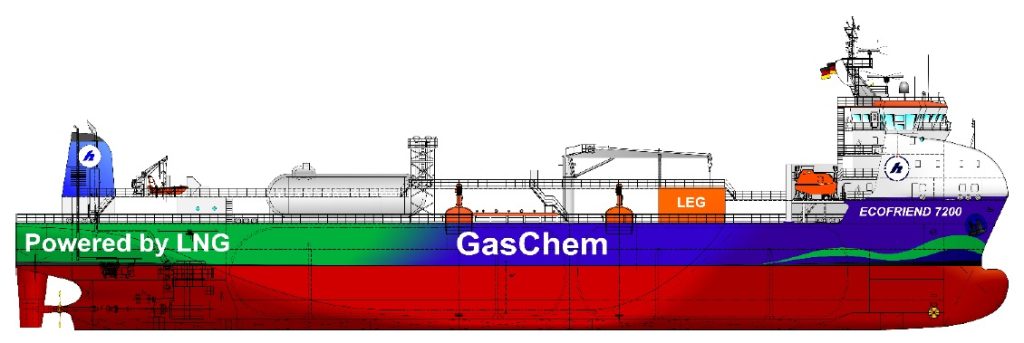BASFはこのほど、農業従事者がCO2排出量を削減する活動を追跡し、その活動実績により利益を得られる、グローバルカーボンファーミングプログラムを開始する。持続可能な農業を促進し、種子から形質、革新的な化学的・生物学的農薬製品、デジタルファーミングや施肥管理ソリューションまで、同社の生産者向け総合ポートフォリオを最大限活用し、持続可能で炭素効率の良い農業を支援する。
世界のCO2排出量の約20%は農業によるもの。2030年までに小麦、大豆、米、菜種、トウモロコシ生産で作物1t当たりのカーボンフットプリントを30%削減するという、同社アグロソリューション事業本部の目標達成の一環として、今年から段階的に進める。
昨年、持続可能な農業、土壌への炭素隔離、農場レベルでの排出量削減に向けた複数年にわたる初のフィールドテストを開始。「ザルビオ」プラットフォームを活用したデジタルファーミングと「アグバランス」(国際認定された同社の持続可能性評価ツール)を活用したサービス提供につなげ、データの評価や情報に基づく意思決定によりサステナビリティを向上させていく考えだ。
改善を指示・評価するサステナビリティツールに基づいてバランスの取れた意思決定を支援し、農場でのCO2排出量を削減し、土壌への炭素隔離を促進する。さらに認証機関からカーボンクレジットを得られるグローバルな仕組みを作り、CO2排出量削減の取り組みにより報酬を得られるようにする。生産者はネットゼロを推進し地球温暖化を抑制する上で重要な役割を担っており、収量向上のための総合的なアプローチにより、農場経営の柔軟性を高め、生産性を向上できるように支援するとしている。