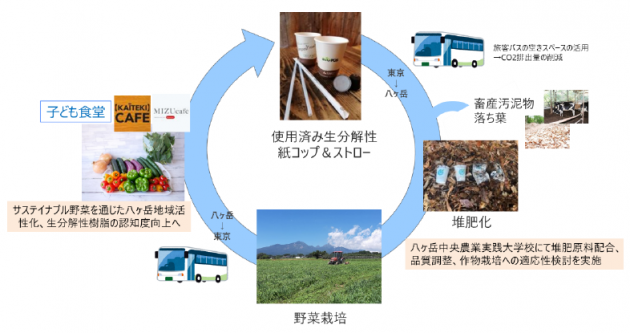帝人は27日、同社グループのTAT(米国)が、仏拠点において、生産性、外観性、寸法・品質安定性に優れるシートモールディングコンパウンド(SMC)製造設備による商業生産を開始したと発表した。
なお、設備投資額は約7億円。自動車向け複合成形材料事業を展開するTATは、コンポジット部品の北米最大のサプライヤーとしての地位を確立し、主にガラス繊維を用いた自社開発のSMCを製造している。
今回、フランスで商業生産を開始したことで、ポルトガルやチェコの成形拠点と共に欧州におけるバリューチェーンを確立。これにより自動車産業の主要市場の1つである欧州域内において、北米と同様に材料から成形までの一貫生産体制を実現した。今後、TATは、開発中の低VOC(低揮発性有機化合物)などを使用した製法も加え、優位性の高いコンポジット製品を拡大展開することにより、欧州の自動車メーカーのニーズに対応していく。
帝人グループは、自動車業界が求める軽量、安全で、エネルギー効率や耐久性に優れる部品をグローバルに提供することができる世界有数のリーディングカンパニーとして、さらに確固たる地位を確立していく。また、バリューチェーン全体のライフサイクルにおける、CO2排出量削減に向けた技術開発や様々な取り組みにも注力し、2030年近傍には、自動車向け複合成形材料事業の売上を20億ドル規模へと拡大していく。