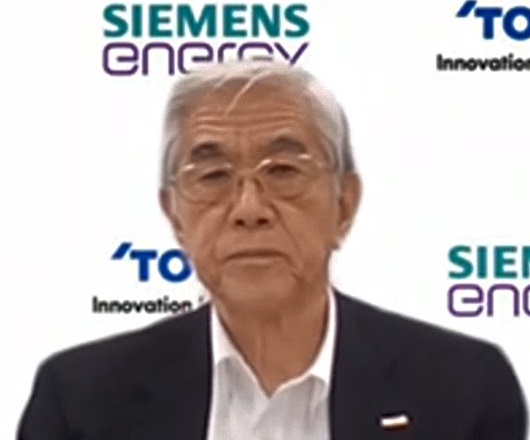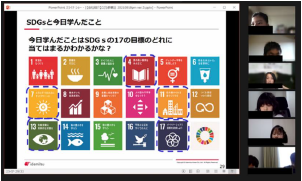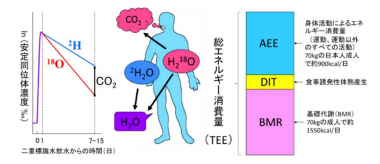住友化学は8日、リサイクル技術を活用して生産するプラスチック製品について、新ブランド「Meguri(メグリ)」(商標登録中)を立ち上げると発表した。同ブランドの普及を通じて、温室効果ガス(GHG)排出削減をはじめとする環境負荷低減への貢献を目指す。

「Meguri」は、ケミカルリサイクル(CR)やマテリアルリサイクル技術により生産するポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)、アクリル樹脂などの様々なプラスチック製品を対象としたブランド。
同社が先月に公表した、愛媛工場(愛媛県新居浜市)に建設予定のCR実証設備から得られる再生アクリル樹脂を皮切りに、積水化学工業と共同で開発中のごみを原料とするPEや、廃プラを再資源化する自動車部材向けのPPコンパウンドなども「Meguri」としての展開を予定する。顧客や同業他社、自治体などとの使用済みプラ製品の回収を含めた連携体制の構築も図りながら同ブランドの製品ラインアップを拡充し、生産・販売を増やしていくことで、循環型社会実現の一助を担っていく考えだ。
「Meguri」は、住友化学の次世代を担う若手社員が議論を重ね、「3つの『めぐり』を未来へつなぐ」という思いを込めて命名。「資源循環」と「人とのめぐり会い」に加え、煙害克服のため、銅製錬時に発生する亜硫酸ガスから肥料を製造する目的で設立された同社にとって、事業を通じて社会課題を解決するという創業の精神への「原点回帰」の意味が込められている。また、ブランドロゴに併記する「Circularity for all」は、循環型社会の実現への貢献に向けた固い決意を表現した。
住友化学は、経営として取り組む重要課題(マテリアリティ)の1つにプラスチック資源循環を含めた環境負荷低減への貢献を掲げている。今後も、グループを挙げて経済価値と社会価値を一体的に創出し、持続的な成長とともに、サステナブルな社会の実現に貢献していく。