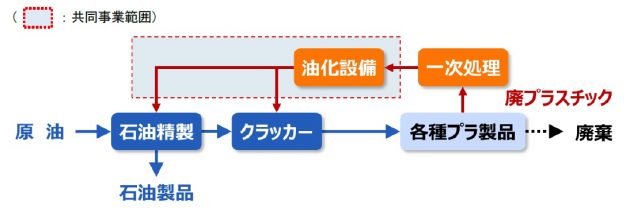ENEOSはこのほど、静岡市との間で「静岡市清水区袖師地区を中心とした次世代型エネルギーの推進と地域づくりに係る基本合意書」を締結したと発表した。

両者は相互に連携し、ENEOSの清水製油所跡地(清水油槽所内遊休地)を中心に「次世代型エネルギー供給プラットフォーム」を構築するとともに、「まち」と「みなと」が一体となった魅力的で持続可能な地域づくりを進める。
具体的には、ENEOSは再生可能エネルギーをはじめとした地産地消による自立型エネルギーの供給体制を整備し、蓄電池などの最新技術を活用したエネルギーの効率化・多様化、災害時のレジリエンス向上、モビリティサービスを含めた新たな付加価値サービスを提供する、次世代型エネルギー供給プラットフォームを構築。静岡市はそれに協力する。同合意により、地域との相乗効果を生む事業開発を推進し、2024年度ごろの運用開始を目指す。
昨年7月、ENEOSは静岡県と次世代型エネルギーの推進と地域づくりに係る基本合意書を締結。同製油所跡地を中心に次世代型エネルギー供給プラットフォームの構築に向けた検討を進めており、その中で静岡市とも協議を行ってきた。ENEOSは2040年に自社が排出するCO2のカーボンニュートラルを掲げ、一方、静岡市は2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた取り組みの推進を表明している。今後は静岡県、静岡市、ENEOSの3者で相互に連携を図り、脱炭素社会の実現に貢献する地域づくりを行っていく。