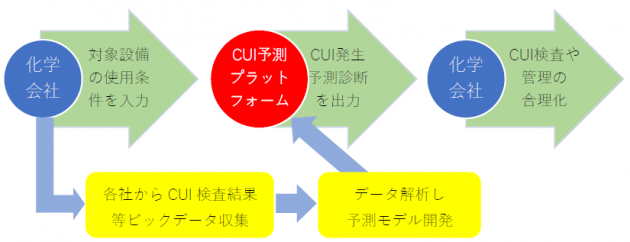積水化学工業の調査研究機関である住環境研究所は、「ニューノーマル(新常態)時代の住まい方に対する意識調査」を実施した。
近年、情報技術の発達や働き方改革などにより生活者の価値観が変化。それに伴い〝してみたい暮らし方〟や〝暮らしたい場所〟も多様化し、また〝新しい暮らし方〟も多く現れている。こうした中、コロナ禍によって、リモートワークやオンライン会議の普及、自粛による在宅時間の増加など、世の中がさらに大きな変化を強いられている。
今回の調査(昨年10月実施)は、住宅購入者の多数を占める20~50代の男女既婚者を対象に、新常態の時代も見据えたこれからの「住まい方」に対する生活者の意識を明らかにすることを目的に実施された。その結果、住宅取得の主役となる20代は、新しい暮らし方では「技術的最先端の暮らし」や「職住一致」、従来からある暮らし方では、「エコな暮らし」や「二世帯居住」、暮らしたい場所では、「郊外」を筆頭に多様な場所での暮らし、に関心が高いといった特徴が見られた。
同研究所は、「20代が様々な暮らし方・暮らしたい場所に対し関心をもてることは、住まい方の多様性を許容する「柔軟性」のため」と分析。そして「これまでの生活や慣習が加速度的に変化を遂げていくウィズコロナ、ニューノーマルの時代では、しなやかさ(レジリエンス)が必要になってくる。そのような時代を乗り切っていくためには、20代に見られるような住まい方への「柔軟性」も原動力となっていくのではないか」との見解を示している。