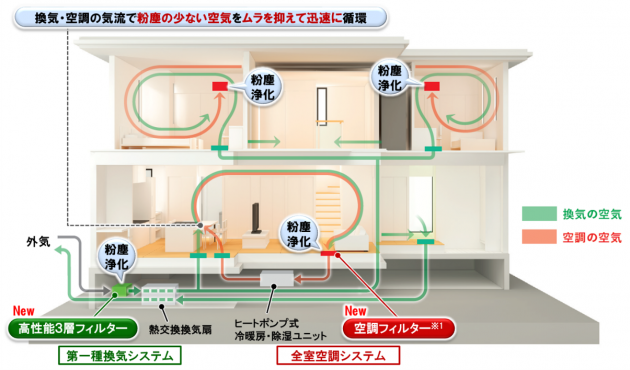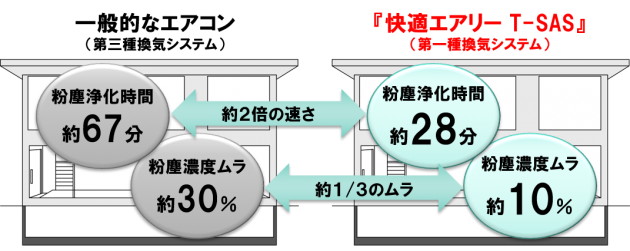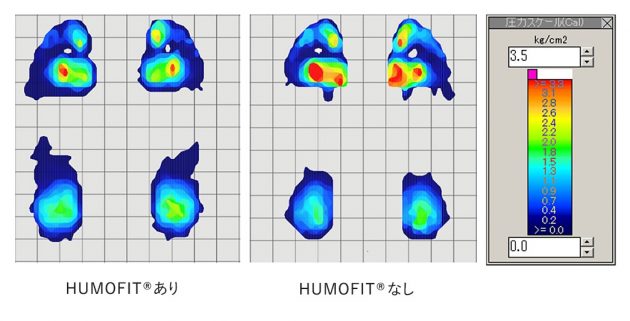三井化学は22日、日本物流団体連合会が主催する「第22回物流環境大賞」について、旭化成、山九と合同で「特別賞」を受賞したと発表した。

3社は千葉県と広島県・山口県間で行う樹脂の長距離輸送を、トラックを使う陸上輸送から、より環境負荷の少ない船舶を利用した海上輸送に切り替える「モーダルシフト」を開始。山九の定期内航コンテナ船と海上コンテナを活用し、往路は三井化学が、復路は旭化成がラウンドユース(往復利用)することで空荷状態の抑制に取り組んでいる。
物流については、輸送時のCO2排出量削減や長距離トラックのドライバー不足解消が大きな課題となっている。今回の取り組みによりCO2排出量を4割削減し、ドライバーの拘束時間を8割削減した。さらに、サイドオープン型コンテナを採用することで、スロープの有無にかかわらず積み下ろし倉庫の選択が広がり、また、積み下ろし作業上の安全性と効率性が向上した。
三井化学は「ホワイト物流」推進運動にも賛同するなど、物流面での取り組みを拡充させている。今後も、他の企業との協働を拡大し、物流環境変化に柔軟に対応できる強靭なサプライチェーンを追求していく考えだ。
なお、物流環境大賞は2000年に創設。物流部門の環境保全推進や環境意識の向上などを図り、物流の健全な発展に貢献した団体・企業または個人を表彰している。