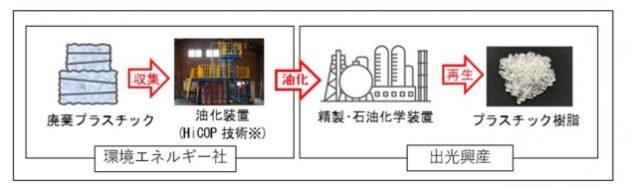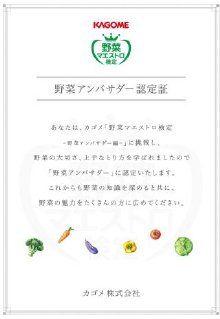カネカはこのほど、「カネカ生分解性ポリマーGreen Planet」を使用したストローがファミリーマートに採用されたと発表した。先月末からファミリーマートの「ファミマカフェ」と紙パック飲料向けストローとして、全国の一部店舗で順次導入されている。

ファミリーマートは環境に関する中長期目標「ファミマecoビジョン2050」の中で、環境配慮型素材の使用割合を高めることにより環境対応の推進を目指している。
同ポリマーはカネカが開発した100%植物由来の生分解性ポリマー「PHBH」。海水中で生分解する認証「OK Biodegradable MARINE」(30℃の海水中で生分解度が6カ月以内に90%以上になる)を取得しており、幅広い環境下で優れた生分解性を示す。今回、環境負荷低減に貢献する点が評価されて採用された。
今後も「カネカは世界を健康にする。」という考えの下、ソリューションプロバイダーとしてグローバルに価値を提供し、「Green Planet」の展開を通じて環境汚染問題の解決に貢献していく考えだ。