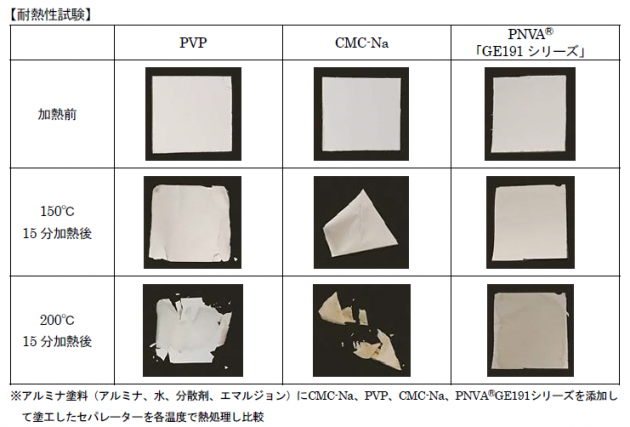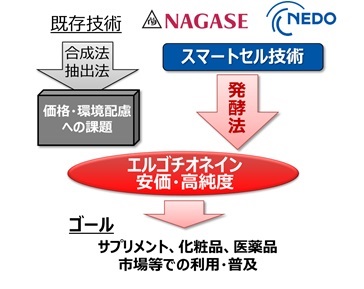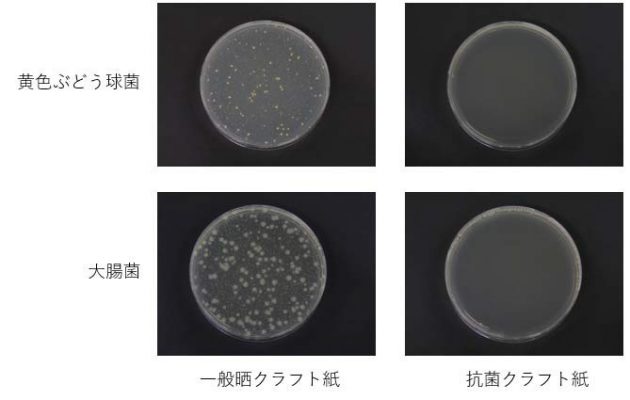BASFはこのほど、子会社のトライナミクス(ドイツ、ルートヴィッヒスハーフェン)が日本市場向けの赤外線センサー事業の技術サポート体制と販売ネットワーク強化の一環で、アイ・アール・システム(東京都多摩市)と赤外線センサーの販売代理店契約を締結したと発表した。トライナミクス社開発・製造の赤外線センサー「ヘルツシュテュック」をアイ・アール・システムが日本市場で販売するもので、相互の営業活動を制限しない非独占的な販売代理店の形態とし、自由な営業活動による相乗効果を狙う。
アイ・アール・システムは赤外線技術分野の高い専門知識と日本市場での多様な産業分野との販売ネットワークをもち、両社の協力関係強化により、販売チャネルの一層の拡大を図る。なおBASFジャパン内に設けた同赤外線センサー事業推進チームは事業拡大を目指し、商品供給も開始している。
トライナミクスは2015年設立の赤外線センシングや3Dイメージング、測距技術におよぶ幅広い先進技術と製品ポートフォリオの開発を進め、多様な科学技術分野を専門とする100人超の開発チームを擁する。
同赤外線センサーは硫化鉛/セレン化鉛(PbS/PbSe)光導電素子で、波長1~5㎛の近赤外線の検出が可能。独自の薄膜封止技術により、使用環境中の水分や酸素による品質劣化を低減し、ベアチップ状態での商品供給によりセンサー素子の薄型化と電子プリント基板への表面実装を可能にし、赤外分光器、ガスセンシング、炎・火花検出、火炎制御、医療機器やIoTセンサーシステムなどの様々な産業領域や用途で優れた性能を発揮する。
日本は赤外線センサーを含むハイテク産業の世界最大級の市場の1つで、産業用システム、医療機器、民生用機器などの領域で世界的リーディングカンパニーが数多く存在する重要な市場であるとし、赤外線センサーとそのソリューションにより一層の顧客支援を目指す考えだ。