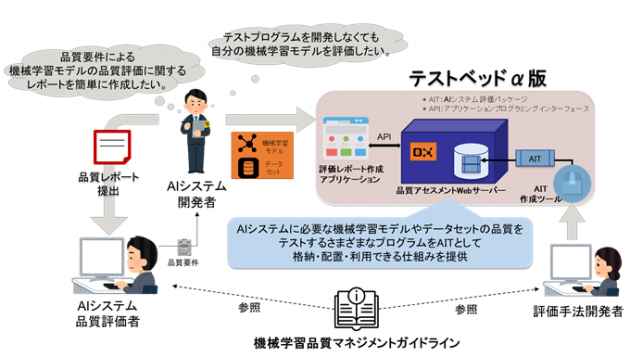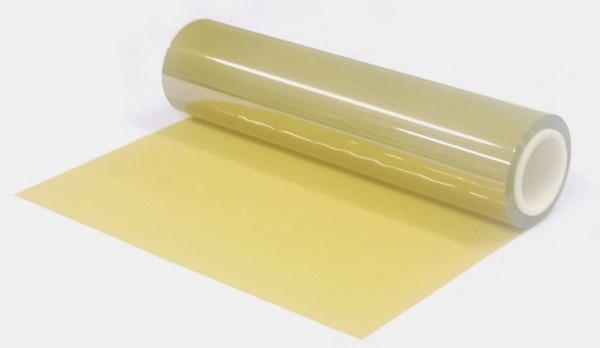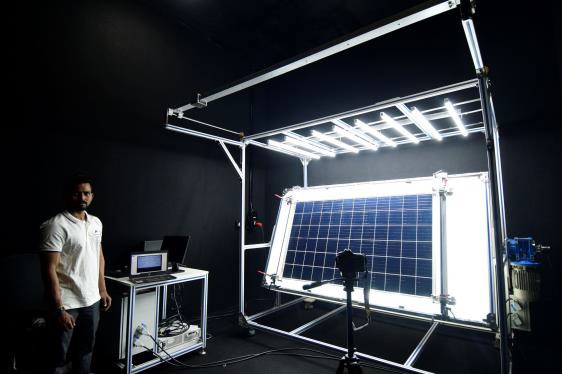東ソーは9日、グループ会社である東ソー物流(山口県周南市)が、新エチレン輸送船「翔陽(しょうよう)」を今月7日に竣工したと発表した。エチレンは、極めて可燃性と引火性が高く、十分な安全対策を実施する必要があり、既存船舶が老朽化していることから、安全・安定輸送を継続する目的で更新した。

同船は、ガス状のエチレンをマイナス103℃まで冷却して液体で輸送できる国内でも数少ない特殊な船舶。また、環境にやさしい設計が採用され、最適な船型およびエコステータ(プロペラ効率を改善させる整流板)や摩擦抵抗低減型塗料などによる推進性能の向上、さらに、トラックコントロール(自動航路維持システム)付きの電子海図装置搭載による最適航路が実現されるなど、燃料消費量の低減を実現している。
同社グループは、高度化・多様化・広範化する物流ニーズに対応するため、グローバルサプライチェーンの強化を図るとともに、物流の効率化や環境にやさしい物流事業を推進することで、地球温暖化防止などの環境保全にも配慮し、持続可能な社会の実現に貢献していく。