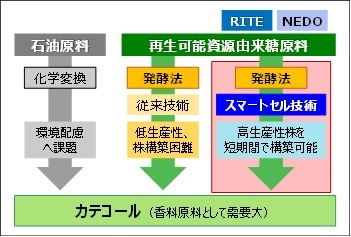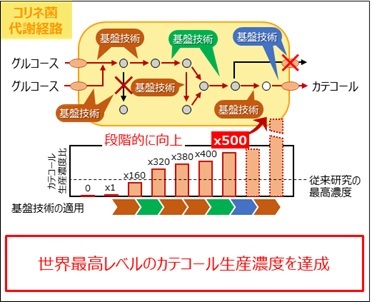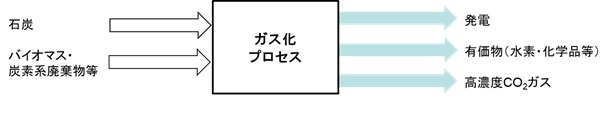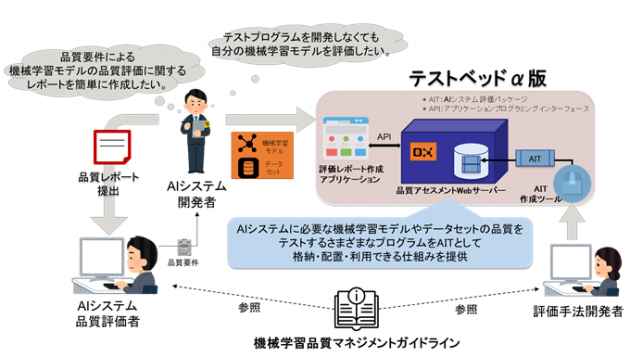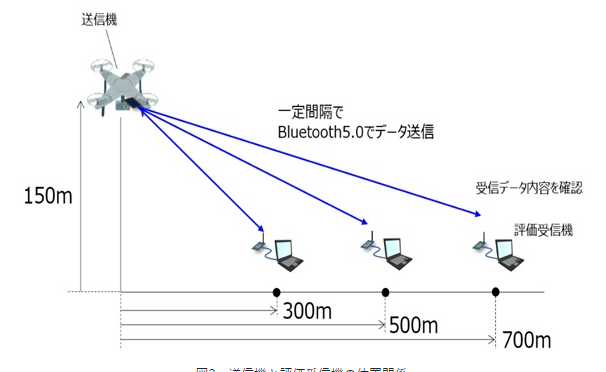新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と住友電気工業はこのほど、大型定置用蓄電池「レドックスフロー(RF)電池」(容量8㎿h)で平常時・災害時の併用運転(デュアルユース)を実現する世界初の実証事業を行うと発表した。米国カリフォルニア州で取り組んできた、送配電網での電力品質向上を目的とする実証事業を延長し、実配電網の一部でマイクログリッドを構築し、平常時は電力取引で収益を得ながら災害時には自立電源として電力を供給する手法などを検証する。

NEDOは同州との協定の下、2015年に住友電工と現地の大手電力会社SDG&Eとともに同州サンディエゴに設置したRF電池設備による送配電網の電力品質向上の実証事業を進め、2018年より系統運用者CAISOとの電力取引運用を始めた。
RF電池はバナジウムなどのイオン(活物質)の酸化還元反応により充放電を行い、充放電のパターンやサイクル数によらず長寿命で大型化に適している。充電残量をリアルタイムで計測できるため、自由度の高い入札パターンで、エネルギー市場(電力量の取引市場)とアンシラリーサービス市場(需給バランスの監視、系統運用、電圧・周波数の調整など)の両市場で収益を上げる入札戦略の開発、実証を行ってきた。
今回、既設のRF電池を自立電源としたマイクログリッドを形成し約70軒の実需要家に電力供給し、技術的課題を検証する。平常時はCAISOとの電力取引で収益を得て、災害時にはマイクログリッドに電力供給を行い、蓄電池の価値を高める狙いだ。この技術は無電化地域の太陽光や風力発電施設を併設したマイクログリッド、離島での再生可能エネルギーによる電力供給にも適用できる。
森林火災の多発が予測される秋までにシステムを構築し、12月まで実証を行う。その後実証成果を生かし、RF電池の普及を通じた電力システムのレジリエンス向上、再生可能エネルギー導入拡大、温室効果ガス排出削減に貢献するとしている。